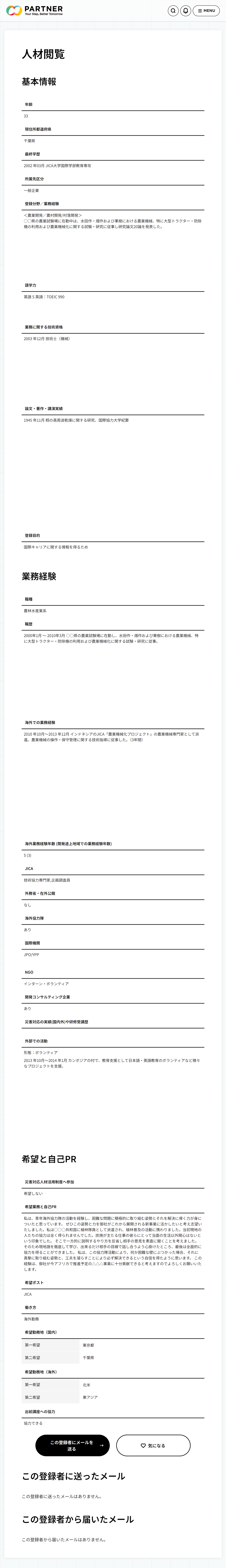バッグ店で働く=国際協力活動!? ファッション、ビジネスを通して、途上国の課題解決の一端を担いたい ~協力隊の任期を終えて3年~

濱口 香織さん
民間企業
/
株式会社マザーハウス あべのsolaha店店長
/
30代
キャリア年表
インタビュー
海外協力隊の任期を終えて3年、濱口香織さんは、バッグやアパレル製品を途上国で生産し、日本や台湾など、合計19店舗で販売する株式会社マザーハウス(本社東京・台東)あべのsolaha店(大阪・阿倍野)の店長として働く。帰国後の就職活動では進路に迷うこともあったが、
紆余曲折を経て、“心から打ち込める仕事”にたどり着いた。
「いまは任された店舗を軌道に乗せることが第一。いつかは途上国に行き、その土地にある素材や技術、人の魅力を形(ビジネス)にしていきたい」と語る。
きっかけはストリートチルドレン、新卒で協力隊へ
濱口さんが途上国に興味をもったのはいまからおよそ10年前、高校の世界史の授業だった。
教師は元バックパッカー。自身が撮ったビデオを授業で見せてくれた。
ひとつのシーンが濱口さんの脳裏に焼き付いた。インドのストリートチルドレンの映像だ。
「子どもが路上で暮らすということがイメージできなかった。どうしてそんな状況が生まれるのか。自分なりにいろいろ調べてみた」と話す。
濱口さんは高校卒業後、筑波大学国際総合学類に進学。大学2年の夏にインドを初めて訪問した。また卒論の
テーマを「都市部貧困層と『路上文化』―インド・コルカタの事例から―」に決め、インドでフィールドワークも重ねる。
「イメージと現実は違った」と濱口さん。路上で暮らす人の多くが地方出身者だったこともあり、今度は、
文化や村に強い興味をもった。
知りたいことを追求する姿勢が濱口さんを協力隊へと突き動かす。
「大学で文化人類学や社会開発論を学んでいた。その中で、学問を実践に落としたいとの思いがあった。
国際協力の分野で働くのであれば、『現場経験2年』と『修士号』は必須だと認識していたので、協力隊への参加を後回しにする理由はないと考えた」
濱口さんは卒業前に就職活動をほとんどしなかった。4年生の春に協力隊(職種は村落開発普及員)試験を
受けた。合格。2009年3月に大学を卒業し、6月にはインドの隣国ネパールへ飛んだ。
教師は元バックパッカー。自身が撮ったビデオを授業で見せてくれた。
ひとつのシーンが濱口さんの脳裏に焼き付いた。インドのストリートチルドレンの映像だ。
「子どもが路上で暮らすということがイメージできなかった。どうしてそんな状況が生まれるのか。自分なりにいろいろ調べてみた」と話す。
濱口さんは高校卒業後、筑波大学国際総合学類に進学。大学2年の夏にインドを初めて訪問した。また卒論の
テーマを「都市部貧困層と『路上文化』―インド・コルカタの事例から―」に決め、インドでフィールドワークも重ねる。
「イメージと現実は違った」と濱口さん。路上で暮らす人の多くが地方出身者だったこともあり、今度は、
文化や村に強い興味をもった。
知りたいことを追求する姿勢が濱口さんを協力隊へと突き動かす。
「大学で文化人類学や社会開発論を学んでいた。その中で、学問を実践に落としたいとの思いがあった。
国際協力の分野で働くのであれば、『現場経験2年』と『修士号』は必須だと認識していたので、協力隊への参加を後回しにする理由はないと考えた」
濱口さんは卒業前に就職活動をほとんどしなかった。4年生の春に協力隊(職種は村落開発普及員)試験を
受けた。合格。2009年3月に大学を卒業し、6月にはインドの隣国ネパールへ飛んだ。
ネパールの女性組合を支援、“あるもの”を活用する
濱口さんの配属先は、ネパール西部のタナフ郡女性開発事務所だった。取り組んだのは、形骸化していた現地の「女性協同組合」の活性化だ。 協同組合や保健衛生の専門家を呼んで組合員に向けて集中講義を開いたり、組合員を簿記会計や家畜飼育のトレーニングにカトマンズや郡庁へ派遣したりした。組合活動に参加できない女性に対しては、女性協同組合のヤギ銀行システムにヤギを貸すよう仲介したり、村にトイレを設置するよう村役場へ働きかけたりもした。
そのなかで学んだことは2つある。
1つは、“ないもの”ではなく、“あるもの”に目を向けることの大切さだ。ネパール人にはネパールの事例が一番響く。ネパールにもモデルや資源はある。バングラデシュや日本の話をしてもピンとこなかった女性たちが、
同じ郡のアクティブな女性組合を視察したときは強い刺激を受けていた。
バイオ燃料の原料となる植物(ヤトロファ)が自分の村に自生していると気づいた女性は「視察先の女性組合と協力して事業ができないか」と提案し、また別の女性は「SLC(中等教育修了資格)を取りたい」と話した。濱口さんは「女性たちのほうから具体的なアクションが提示されたのは初めて。とても驚いた」という。
そのなかで学んだことは2つある。
1つは、“ないもの”ではなく、“あるもの”に目を向けることの大切さだ。ネパール人にはネパールの事例が一番響く。ネパールにもモデルや資源はある。バングラデシュや日本の話をしてもピンとこなかった女性たちが、
同じ郡のアクティブな女性組合を視察したときは強い刺激を受けていた。
バイオ燃料の原料となる植物(ヤトロファ)が自分の村に自生していると気づいた女性は「視察先の女性組合と協力して事業ができないか」と提案し、また別の女性は「SLC(中等教育修了資格)を取りたい」と話した。濱口さんは「女性たちのほうから具体的なアクションが提示されたのは初めて。とても驚いた」という。
女性120人で役場に直訴、弱者向け予算の要求も
もう1つの学びは、何をするにもベースは「人と人との信頼関係」だということ。自分が動くのは簡単だ。
だが周囲の人(濱口さんの場合は村落部の女性たち)に動いてもらうことは難しい。根気と諦めない姿勢が欠かせない。
女性たちが動き出した、と濱口さんが実感したのは、一緒に活動を始めてから1年以上経ってからだ。女性組合の運営委員会(11名)のミーティングに人が集まるようになり、女性120人の集団で村役場に行き、社会的弱者
支援予算(女性、子ども、低カースト、少数民族を対象とした予算。だが女性の声は無視されていた)を適正に
配分するよう直訴した。
「ネパールの女性たちを私が見ていたのと同じように、彼女たちも私のことを信頼できる人間かどうか見極めていた。村に住み込んで活動していたから、私は信頼関係を築きやすかったと思う」
ネパールには驚く慣習がたくさんあった。力仕事は女性の仕事であること、海外に出稼ぎに行くため男性は
留守が多いこと、民族によっては生理中の女性は「穢れ」とされ、自宅に入ることが許されず、屋外で寝なければならないこと、妊婦の多くは病院ではなく家で出産していたことなどだ。
「協力隊を経験して自分が劇的に変わったという感覚はない」と自己分析する濱口さん。
「ただ、自分が思っていた “当たり前” がそうでない場合もあることを知った。日本というチャレンジできる環境に生まれたからこそ、どんな生き方をするか、ひとつひとつの決断は疎かにしたくないとの思いを強くした」
だが周囲の人(濱口さんの場合は村落部の女性たち)に動いてもらうことは難しい。根気と諦めない姿勢が欠かせない。
女性たちが動き出した、と濱口さんが実感したのは、一緒に活動を始めてから1年以上経ってからだ。女性組合の運営委員会(11名)のミーティングに人が集まるようになり、女性120人の集団で村役場に行き、社会的弱者
支援予算(女性、子ども、低カースト、少数民族を対象とした予算。だが女性の声は無視されていた)を適正に
配分するよう直訴した。
「ネパールの女性たちを私が見ていたのと同じように、彼女たちも私のことを信頼できる人間かどうか見極めていた。村に住み込んで活動していたから、私は信頼関係を築きやすかったと思う」
ネパールには驚く慣習がたくさんあった。力仕事は女性の仕事であること、海外に出稼ぎに行くため男性は
留守が多いこと、民族によっては生理中の女性は「穢れ」とされ、自宅に入ることが許されず、屋外で寝なければならないこと、妊婦の多くは病院ではなく家で出産していたことなどだ。
「協力隊を経験して自分が劇的に変わったという感覚はない」と自己分析する濱口さん。
「ただ、自分が思っていた “当たり前” がそうでない場合もあることを知った。日本というチャレンジできる環境に生まれたからこそ、どんな生き方をするか、ひとつひとつの決断は疎かにしたくないとの思いを強くした」
初めての就活、自分を見失った‥‥
濱口さんは11年6月、日本に帰国した。すぐに本格的な就活を始める。ところが苦労の連続。「ネパールでいろんな経験をしたことで、いろんなことに関心をもつようになった。だから、自分自身が何をしたいのか見えなくなってしまっていた」と当時の状況を振り返る。
新卒で協力隊に参加したため社会人経験はゼロ。大学時代の友人が企業で活躍する姿を見て、焦った。
「とりあえずは少しでも興味がもてるところに就職しよう。その後のことはそれから考えればいい」との
スタンスで、日本社会に復帰することを優先した。
地域活性化に携わってきた経験から「地元」そして「海外」をキーワードに就職活動を開始した。だが企業の面接は厳しかった。「国際協力一辺倒の経歴なのに、どうしてここにきて民間企業ですか」「あなたにはもっと別にあうところがあると思いますよ」などと言われた。受験した地元のテレビ局は落ちた。
日本社会への復帰を優先させようという思いで始めた就職活動だったが、進めていくにつれて国際協力への
未練があることに気づいた。協力隊の経験を単なる思い出にしたくない、日本社会に復帰できないかもしれないというリスクを負ってでも本当に興味関心があることに従事したい、という想いが徐々に浮き彫りになった。
食品メーカーの海外営業職を受けていたが並行して国際協力機構(JICA)の企画調査員も受けた。
食品メーカーの方が先に結果(採用!)が出た。JICAの試験も受けていることを伝えてあったため、比較検討の上での回答でよいと言ってくれた。担当者は面接のときから迷っている濱口さんに真摯に向き合ってくれていた。中途半端な気持ちで対応してはいけないと感じ、JICAの試験結果が出る前であったが断った。
最終的にはJICAの企画調査員に合格、企画調査員(半年契約)としてネパール・カトマンズに赴任した。
企画調査員として働く間に、次の身の振り方について答えを見つけ出すつもりだった。
企画調査員の仕事は自分の力不足を感じる場面が少なからずあった。ネパール政府の高官や他のドナー(援助国・機関)との調整や意見交換する機会がひんぱんにあり、マクロの視点から物事をとらえる難しさに葛藤を覚えた。「隊員時代は山村の女性たちの “小さな声” に耳を傾けていたから、私にとってはギャップが大きかった」
新卒で協力隊に参加したため社会人経験はゼロ。大学時代の友人が企業で活躍する姿を見て、焦った。
「とりあえずは少しでも興味がもてるところに就職しよう。その後のことはそれから考えればいい」との
スタンスで、日本社会に復帰することを優先した。
地域活性化に携わってきた経験から「地元」そして「海外」をキーワードに就職活動を開始した。だが企業の面接は厳しかった。「国際協力一辺倒の経歴なのに、どうしてここにきて民間企業ですか」「あなたにはもっと別にあうところがあると思いますよ」などと言われた。受験した地元のテレビ局は落ちた。
日本社会への復帰を優先させようという思いで始めた就職活動だったが、進めていくにつれて国際協力への
未練があることに気づいた。協力隊の経験を単なる思い出にしたくない、日本社会に復帰できないかもしれないというリスクを負ってでも本当に興味関心があることに従事したい、という想いが徐々に浮き彫りになった。
食品メーカーの海外営業職を受けていたが並行して国際協力機構(JICA)の企画調査員も受けた。
食品メーカーの方が先に結果(採用!)が出た。JICAの試験も受けていることを伝えてあったため、比較検討の上での回答でよいと言ってくれた。担当者は面接のときから迷っている濱口さんに真摯に向き合ってくれていた。中途半端な気持ちで対応してはいけないと感じ、JICAの試験結果が出る前であったが断った。
最終的にはJICAの企画調査員に合格、企画調査員(半年契約)としてネパール・カトマンズに赴任した。
企画調査員として働く間に、次の身の振り方について答えを見つけ出すつもりだった。
企画調査員の仕事は自分の力不足を感じる場面が少なからずあった。ネパール政府の高官や他のドナー(援助国・機関)との調整や意見交換する機会がひんぱんにあり、マクロの視点から物事をとらえる難しさに葛藤を覚えた。「隊員時代は山村の女性たちの “小さな声” に耳を傾けていたから、私にとってはギャップが大きかった」
マザーハウスに就職、店長の業務は“隊員時代のよう”
2度目のネパールから帰国したのは12年8月。濱口さんは、ビジネスの現場を経験したい、と思うようになっていた。消費の形を変えれば、世界は変わると考えたからだ。
就活は2度目。今回は方向が明確だった。「『ネパール』と『ビジネス』がクロスする仕事はないかなと考えたところ、マザーハウスが真っ先に思い立った。スーッと心に落ちてくるものがあった。ここだ!と直感した。
これは初めての感覚。いままで積み重ねてきたものがつながると思った」
濱口さんは希望通り、マザーハウスに12年12月に入社。最初は本店(秋葉原)と小田急新宿店で店舗スタッフとして働く。13年10月から東銀座店の副店長、14年2月からはあべのsolaha店の店長を任されている。
店長の業務は悩みが尽きない、と濱口さん。スタッフに仕事のやり方をどう伝えていけばいいのか。自分らしいコミュニケーションの方法やマネジメントの仕方を確立したいが、まだできずにいる。
「店長として駆け出しのいまの自分は、ネパールの村に入ったばかりの隊員時代の自分と重なる。どうしたら自分の意思が相手に伝わるだろうか、と追求する作業は、ネパールも日本も同じ。いまから思うと、ネパールの女性たちはストレートに自分たちの気持ちを表現してくれたので、それに助けられた。日本人は本音を出さない分、難しい」
就活は2度目。今回は方向が明確だった。「『ネパール』と『ビジネス』がクロスする仕事はないかなと考えたところ、マザーハウスが真っ先に思い立った。スーッと心に落ちてくるものがあった。ここだ!と直感した。
これは初めての感覚。いままで積み重ねてきたものがつながると思った」
濱口さんは希望通り、マザーハウスに12年12月に入社。最初は本店(秋葉原)と小田急新宿店で店舗スタッフとして働く。13年10月から東銀座店の副店長、14年2月からはあべのsolaha店の店長を任されている。
店長の業務は悩みが尽きない、と濱口さん。スタッフに仕事のやり方をどう伝えていけばいいのか。自分らしいコミュニケーションの方法やマネジメントの仕方を確立したいが、まだできずにいる。
「店長として駆け出しのいまの自分は、ネパールの村に入ったばかりの隊員時代の自分と重なる。どうしたら自分の意思が相手に伝わるだろうか、と追求する作業は、ネパールも日本も同じ。いまから思うと、ネパールの女性たちはストレートに自分たちの気持ちを表現してくれたので、それに助けられた。日本人は本音を出さない分、難しい」
夢は駐在員、ファッションで途上国に光を当てたい
マザーハウスはネパールの提携工場でシルクと麻を用いたストールや草木染のバッグなどを作っている(縫製はバングラデシュの自社工場でする)。「店頭にあるストール1本から、村で蚕を育てる女性の顔が見えるのが
マザーハウスの強み。私はネパールで2年半暮らした。だからこそ、店で(顧客に)伝えられること、できることがあると思っている」
濱口さんは、駐在員として生産現場に携わることを希望している。ただマザーハウスでは、スタッフ全員が店舗からスタートするのが基本だ。まずは店長として新店舗を軌道に乗せ、数年後をめどに途上国に“戻って”、
協力隊の経験をビジネスに生かしたいと思っている。
マザーハウスの哲学のひとつに「どこにでも可能性が転がっている。そして誰しもが可能性を持っている」という言葉がある。濱口さんは「ファッションという人々の暮らしに密着したアプローチから途上国の課題を解決する一端を担いたい」と熱く語る。
※本記事は、2012年12月1日時点での情報となります。
マザーハウスの強み。私はネパールで2年半暮らした。だからこそ、店で(顧客に)伝えられること、できることがあると思っている」
濱口さんは、駐在員として生産現場に携わることを希望している。ただマザーハウスでは、スタッフ全員が店舗からスタートするのが基本だ。まずは店長として新店舗を軌道に乗せ、数年後をめどに途上国に“戻って”、
協力隊の経験をビジネスに生かしたいと思っている。
マザーハウスの哲学のひとつに「どこにでも可能性が転がっている。そして誰しもが可能性を持っている」という言葉がある。濱口さんは「ファッションという人々の暮らしに密着したアプローチから途上国の課題を解決する一端を担いたい」と熱く語る。
※本記事は、2012年12月1日時点での情報となります。