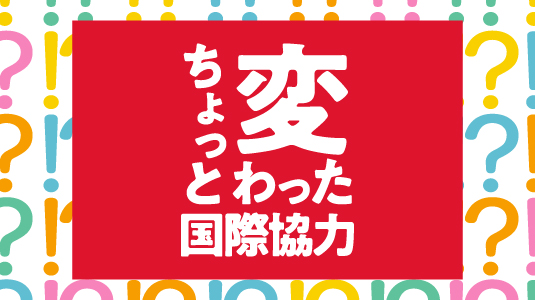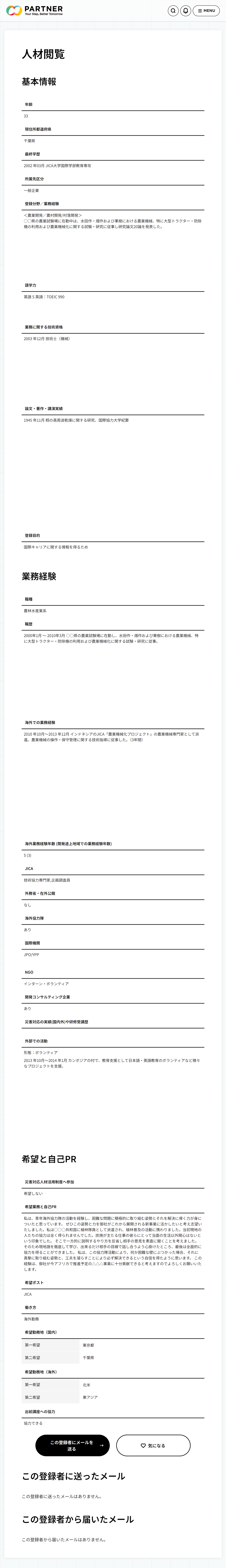どれだけ本気でかかわれるか。やりたいことを周囲に発信し続けることの重要性 ~インターンで得た強みをキャリアに活かす~

服部 圭介さん
NGO / 東北広域震災NGOセンター(国際ボランティアセンター山形) / 20代
キャリア年表
インタビュー
国際協力業界で仕事をしたいと考える人が、将来に渡る自身のキャリアを考え、インターン先に
国際機関を志望するケースは多いだろう。今回登場いただく服部圭介さんはUNDPでのインターンを経て、建設コンサルタント会社に就職。入社直前、ケニアでEASEN(East Africa Social
Enterprise Network)の活動をしている際に東日本大震災が発生し、インターン時の経験を活かすべく、休職して復興プランに従事している。いま起きている事柄に即座に対応しようとするフットワークはいかにして培われたのか。服部さんにうかがった。
【プロフィール】
2011年3月、首都大学東京大学院 都市環境科学研究科修了。同大学院の修士2年次に半年間、国連開発計画(UNDP)のインターンを経験。大学院卒業後、4月に建設コンサルタント会社に入社。
9月からは休職し、現在は
東北広域震災NGOセンター
(国際ボランティアセンター山形、現「認定NPO法人IVY」)
でキャッシュ・フォー・ワーク(1)プロジェクトのプロジェクトマネージャーを務める。
UNDPをインターンに選んだ理由とは?
地元の中小企業支援のプロジェクトを立ち上げる話をしており、少しずつ動き出していました。
しかし、修士の2年の段階でそのプロジェクトに一度ストップがかかってしまい、また家庭のことなどから海外に出られない事情が重なり、日本で出来ることを模索していました。
そこで頭を切り替えて、国連開発計画(UNDP)の東京事務所 (現UNDP駐日代表事務所) にインターン希望として履歴書を送りました。それまで自分が大学院で勉強していたPro-poor Tourism(貧困削減のための
ツーリズム)や開発政策など、興味分野がUNDPの提示する貧困削減スキームと重なり、UNDPの発行する 『人間開発報告書』 などもよく参考にしていたことなどからも、学べるものが多いと判断したためでした。
採用後、広報官の上司のもとで働き、インドネシアの洪水やアフガニスタン問題の広報活動のための資料作成や英訳、プレスリリースやCSR関係の業務に関わりました。
UNDPは大きな組織ですが、東京事務所での仕事はグローイング・サスティナブル・ビジネス(GSB)プログラム(2) のための企業連携の推進やUNDPが実施する事業の日本での広報など、どちらかと言えば裏方の動きが多いです。
インターンで学んだことは何でしょうか?
家族や自身のキャリアを考えたとき、ずっと現地にいるのか。それとも家族や友人といる生活と仕事との
バランスを考えるのか。そういうことも確かめたかったので、国内にある国際機関の動きを間近に見られたのは、とてもよかったと思います。
仕事そのものについてはUNDPという大きな組織だけに、長期にわたるプロジェクトも多い。中には到底達成が困難に思える内容もありましたが、一人ひとりが着実に熱意を持ってプロジェクトを進めていました。
そういう腰の据え方やモチベーションの維持を見るにつけ、「この業界で働くならば、覚悟が必要だな」と思いました。
後に建設コンサルタント会社に入社しましたが、どんなプロジェクトに従事している時でも、自分の中にある情熱は持ち続けながら、やりたいことを自分のスタイルで成し遂げられるだけの人材にならないといけない。
そういった先走る気持ちを抑えて仕事に取り組む姿勢をインターンの間に学んだと思います。
インターン後のキャリアについて聞かせてください。
もらっていました。ビジネスの世界にも興味があったので、それらの仕事を通して会社員としてのスキルも磨きながら、アフリカでのプロジェクトを将来的に再開できればいいと考えていました。
しかし、大学院の研究とインターン、NPOの手伝い等を並列で行なっていた忙しさから、「2足の草鞋は現実的じゃないな」と気づき、建設コンサルタント会社に履歴書を送り、縁あって入社しました。
建設コンサルタント会社は、理系の求人が圧倒的に多いので選択肢は多くはなかったのですが、国際協力の
現場に身を置くことを一番に考えての選択でした。
やりたいことが明確なら、それ以外の道を選ぶのは遠回りですし、「昔は国際問題に熱意を燃やしていた
けど、結局今は全く関わっていないや」と言うような人間になってしまうことは、避けたかったのです。
就職後のキャリア展望は?
入社2日前にケニアから帰国してからは、週末の金曜に現地に入りボランティアをして、月曜の早朝にまた東京に帰る暮らしをしていましたが、平日に東京にいる時間をもどかしく感じていました。海外事業で得たスキームも経験もある会社にいるのに、自国の未曾有の事態に自分は何もできていない。その歯がゆさを感じ、上司に「これから国際協力をやるからこそ、今は日本の被災地で活動したい」と訴え続けていました。
その結果、社の海外事業部が扱っていた数少ない東北関連の調査業務を担当させてもらえることになり、震災や復興の情報を調査して世界に発信する仕事に関わるようになりました。
現地に行く中で、 東北広域震災NGOセンター とのつながりができ、そこがキャッシュ・フォー・ワーク(1)のプロジェクトを推進しようと、7月末にプロジェクトマネージャーを公募していました。
実はUNDP時代にキャッシュ・フォー・ワークの資料を取りまとめたことがあり、その趣旨に共感していた
こともあって、同NGOセンターに応募、採用されました。
入社後間もないことだったので、相当怒られることを覚悟しましたが、会社は外で経験を積むことに前向きで、休職というかたちで快く送り出してくれました。いま携わっているプロジェクトは2012年4月30日までで、その後は会社に復職する予定です。
インターンで培われた強みとは?
現在、気仙沼と石巻の現地事務所にベースを置き、山形の本部や東京を行き来するプロジェクトはスケジュール的にも体力的にもハードです。扱っている内容も、震災で失業した方々の人生に大きく関わる重圧を感じる
内容で、自分自身が潰れてしまわないためには、忍耐と楽観性が必要です。改めてプロジェクトを管理する者としての責任感を持ちつつ、自分の生活や心の安定を保つことについて考えさせられました。
これからインターンを希望する人に向けてのメッセージ。
ウェブサイトを活用してタイムリーな空席情報を集め、募集のタイミングに上手く乗るのが主流でしょうか。
でも、どうしてもここに行きたいという場所やこれがやりたいということがある場合は、募集が無くても履歴書を送ってみて熱意を伝えるというのも一つの手段です。イレギュラーな形の採用は、インターンに限らずよく耳にする話です。
また、国際協力業界に就職するのであれば、実際にその仕事についた時の生活のペースを想定しておいたほうがいいと思います。仕事を始めてから「きつい」と知っても、プロジェクトから、そうそう抜けられるわけではないので、事前に自分のやりたい仕事の内容や量をできるだけ明確に確認しておく必要があるでしょう。
やってみると案外、退屈だったりする場合もあります。インターンはそれをつかむ上で、非常に有効だと思います。
いったんインターンに採用されたなら、盗めるものをとにかく盗む。多くのインターンが金銭的な対価をもらえないのは、それに見合う仕事ができないからだと思われていますが、それならなおのこと、お金をもらっている人と自分の仕事の質の違いをきちんと認識することが大事です。
お金がもらえないからといって、ふてくされるのではなく、どんな仕事にも意味があることなので、どれだけ本気でかかわれるか。そういう態度で仕事に臨み、やりたいことを周囲に発信していれば、自分のキャリアに
必要な情報や知りたいことを自然と教えてもらえるようになると思います。(2011年12月インタビュー実施)
(1)キャッシュ・フォー・ワーク(cash for work):災害地等において被災者を復興事業に雇用し、賃金を
支払うことで、被災地の円滑な経済復興と、被災者の自立支援につなげる、国際協力の手法。
(2)グローイング・サスティナブル・ビジネス(GSB)プログラム:商業的に継続可能でありながら貧困削減と持続可能な開発にも貢献する民間セクターの投資を仲介するプログラム。
※本記事は、2011年12月時点での情報となります。