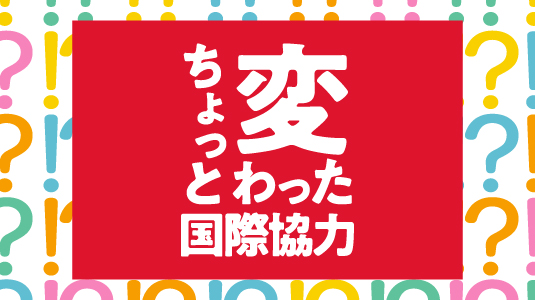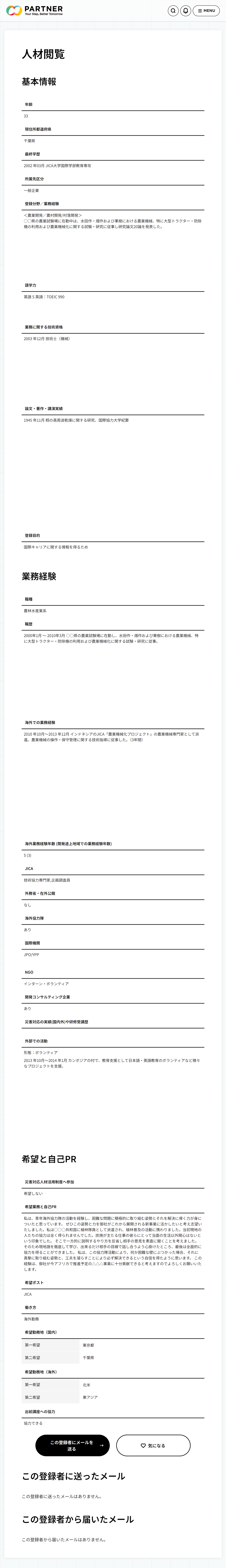稲場 彩さん
政府機関・地方自治体
/
内閣府国際平和協力本部事務局(PKO事務局)
/
30代
政府機関
平和構築
キャリア年表
大学学部生
2000~2005年
国際関係学を専攻。1年休学して約15カ国でフィールドワークを実施。
大学院生
2005~2009年
フランスの大学院で社会政治学と政治哲学を専攻。現代民主主義について研究。
民間企業
2010~2013年
法律事務所や外資系企業で法務事務。
JICA
2013~2015年
カメルーンの科学技術協力案件のプロジェクト専門家(業務調整)。
JICA
2015~2016年
コンゴ民主共和国事務所の企画調査員として電力、鉱物資源、環境セクターを担当。
政府機関
2017~2020年
在フランス大使館の専門調査員。アフリカの政治・治安動向やフランスのアフリカ政策を調査。
政府機関
2020年~現在
国際平和協力に関する調査・研究を実施。
開発、外交、平和協力研究。平和づくりを多角的に学ぶ日々。
国際協力に興味をもったきっかけは何ですか?
私は東京で育ちましたが、母方のルーツが沖縄にあり、戦争の爪痕を身近に感じて育ちました。大学で国際関係学を専攻したのも、人類がなぜ破壊的行為を繰り返すのか、誰かを犠牲にせず助け合って生きていくことはできないだろうか、という問題意識からです。原体験となっているのは、「辺境」や「境界」で何が起こっているかを知るため、1年間休学して東南アジア、中東、アフリカの15カ国を極力陸路で移動した旅での経験です。そこでは、極度の貧困、児童買春、薬物、自爆テロ、紛争など、日本で見ることのなかった生の現実を目にし、これら諸問題に何らかの形で関与していきたいと考えるようになりました。
これまでにどのようなキャリアを歩んでこられましたか?
 大学院修了後、数年間の民間企業勤務を経て、カメルーンとコンゴ民でJICAの開発事業に従事しました。コンゴ民は紛争国ですので、政治・治安情勢の評価が案件形成・実施に大きく影響しました。恒久的平和を作るには息の長い開発支援が必要ですが、そのためにはまず安全確保が不可欠…。このジレンマに直面し、より広い視点から平和構築に取り組む必要があると考え、情勢分析や外交による平和づくりの「いろは」を学ぶため、在フランス大使館の専門調査員に応募しました。担当はアフリカ全域でしたが、各政策意義を理解するためには世界地図を広げて全体を俯瞰しなければならず、マルチ外交や安全保障についての理解が深まりました。
大学院修了後、数年間の民間企業勤務を経て、カメルーンとコンゴ民でJICAの開発事業に従事しました。コンゴ民は紛争国ですので、政治・治安情勢の評価が案件形成・実施に大きく影響しました。恒久的平和を作るには息の長い開発支援が必要ですが、そのためにはまず安全確保が不可欠…。このジレンマに直面し、より広い視点から平和構築に取り組む必要があると考え、情勢分析や外交による平和づくりの「いろは」を学ぶため、在フランス大使館の専門調査員に応募しました。担当はアフリカ全域でしたが、各政策意義を理解するためには世界地図を広げて全体を俯瞰しなければならず、マルチ外交や安全保障についての理解が深まりました。
現在の業務について、具体的にどのようなことを担当されていますか?
大きく分けて3つあります。1つ目は、研究員として国際平和協力に関する調査・研究を行っています。私の場合は、国の防衛外交と、「人道・開発・平和の連携」という平和構築のアプローチを交差させ、治安セクターにおける民軍連携をより高次で実施するためにはどうしたら良いか、ということをテーマにしています。2つ目は、南スーダンの国連PKOミッションに派遣される自衛隊員の研修です。座学の講義と現場で起こり得る事態を想定した演習があり、英語で行われます。3つ目は、平和教育や広報の一貫で行う出前講座です。私はこれまで、高校や大学での日本の国際平和協力の実績を紹介し、国際協力におけるキャリア形成といったテーマでお話させていただきました。
現在の業務でのやりがいや仕事の魅力は何でしょうか?
 平和構築は多面的アプローチにより、人、国、そして平和の機運を作っていくプロセスです。多くのアクターが存在しますが、治安セクター、特に軍の能力強化支援を行えるアクターは限られています。PKO事務局の国際平和協力研究員は、国際機関、他国の関係組織、そして自衛隊が実施する様々な研修や会合に参加する機会があるため、治安セクターにおける国際平和協力についての知見を深め、民軍両方のネットワークを構築することができる、数少ないポストだと思います。また、研究活動通じて、これまでの経験をまとめて課題を整理することができ、次のステップへ進むにあたってキャリアを見つめ直すことができるという意味でも、非常に魅力的です。
平和構築は多面的アプローチにより、人、国、そして平和の機運を作っていくプロセスです。多くのアクターが存在しますが、治安セクター、特に軍の能力強化支援を行えるアクターは限られています。PKO事務局の国際平和協力研究員は、国際機関、他国の関係組織、そして自衛隊が実施する様々な研修や会合に参加する機会があるため、治安セクターにおける国際平和協力についての知見を深め、民軍両方のネットワークを構築することができる、数少ないポストだと思います。また、研究活動通じて、これまでの経験をまとめて課題を整理することができ、次のステップへ進むにあたってキャリアを見つめ直すことができるという意味でも、非常に魅力的です。
今後の目標やキャリアプランをお聞かせください。
和平交渉・対話といった紛争当事者間の仲裁に関心があります。紛争が長期化する要因は様々ですが、和平合意に至っても各約束事が実行されず形骸化し、不信感やフラストレーションが溜まった結果、武力衝突が繰り返されるケースが多く見られます。和平の土台となる当事者間の合意、そして和解のプロセスは、恒久的平和の実現に不可欠なのですが、包括性を確保しつつ、外部の恣意的介入を防ぐことは実際にはとても難しいと思います。今後しばらく現場で経験を積み、ゆくゆくは博士課程に進んで和平プロセスを学術的に整理する時間も作りたいです。常に研究と現場を繰り返しながら平和の実現に貢献していきたいと思っています。
国際協力の道を目指す方に向けてのメッセージをお願いします。
国際協力には様々な関わり方があり、定型のキャリアパスはありません。それだけに、この世界に飛び込む前も飛び込んでからも不安にかられることがあるかもしれません。10年弱続けてきて思うのは、迷ったり立ち止まったり、寄り道した時間も全て糧になるということです。国際協力とは、専門性をもって取り組む「人間学」だと思うので、自らの密度を高め、くっきりとした色合いを培っておくことは、歴史も文化も信念も異なる人々と対峙するにあたり必要な準備だからです。人間には善意もあれば悪意もあります。紛争国では目を背けたくなるような残酷な現実も溢れていますが、人を壊すのも人であれば、癒すのもまた人であることを思うと、やはり一生をかけるに値する仕事だと思っています。


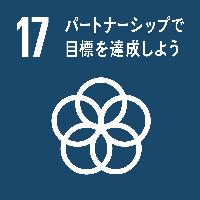
 大学院修了後、数年間の民間企業勤務を経て、カメルーンとコンゴ民でJICAの開発事業に従事しました。コンゴ民は紛争国ですので、政治・治安情勢の評価が案件形成・実施に大きく影響しました。恒久的平和を作るには息の長い開発支援が必要ですが、そのためにはまず安全確保が不可欠…。このジレンマに直面し、より広い視点から平和構築に取り組む必要があると考え、情勢分析や外交による平和づくりの「いろは」を学ぶため、在フランス大使館の専門調査員に応募しました。担当はアフリカ全域でしたが、各政策意義を理解するためには世界地図を広げて全体を俯瞰しなければならず、マルチ外交や安全保障についての理解が深まりました。
大学院修了後、数年間の民間企業勤務を経て、カメルーンとコンゴ民でJICAの開発事業に従事しました。コンゴ民は紛争国ですので、政治・治安情勢の評価が案件形成・実施に大きく影響しました。恒久的平和を作るには息の長い開発支援が必要ですが、そのためにはまず安全確保が不可欠…。このジレンマに直面し、より広い視点から平和構築に取り組む必要があると考え、情勢分析や外交による平和づくりの「いろは」を学ぶため、在フランス大使館の専門調査員に応募しました。担当はアフリカ全域でしたが、各政策意義を理解するためには世界地図を広げて全体を俯瞰しなければならず、マルチ外交や安全保障についての理解が深まりました。
 平和構築は多面的アプローチにより、人、国、そして平和の機運を作っていくプロセスです。多くのアクターが存在しますが、治安セクター、特に軍の能力強化支援を行えるアクターは限られています。PKO事務局の国際平和協力研究員は、国際機関、他国の関係組織、そして自衛隊が実施する様々な研修や会合に参加する機会があるため、治安セクターにおける国際平和協力についての知見を深め、民軍両方のネットワークを構築することができる、数少ないポストだと思います。また、研究活動通じて、これまでの経験をまとめて課題を整理することができ、次のステップへ進むにあたってキャリアを見つめ直すことができるという意味でも、非常に魅力的です。
平和構築は多面的アプローチにより、人、国、そして平和の機運を作っていくプロセスです。多くのアクターが存在しますが、治安セクター、特に軍の能力強化支援を行えるアクターは限られています。PKO事務局の国際平和協力研究員は、国際機関、他国の関係組織、そして自衛隊が実施する様々な研修や会合に参加する機会があるため、治安セクターにおける国際平和協力についての知見を深め、民軍両方のネットワークを構築することができる、数少ないポストだと思います。また、研究活動通じて、これまでの経験をまとめて課題を整理することができ、次のステップへ進むにあたってキャリアを見つめ直すことができるという意味でも、非常に魅力的です。