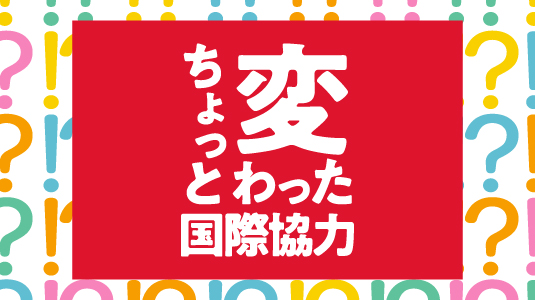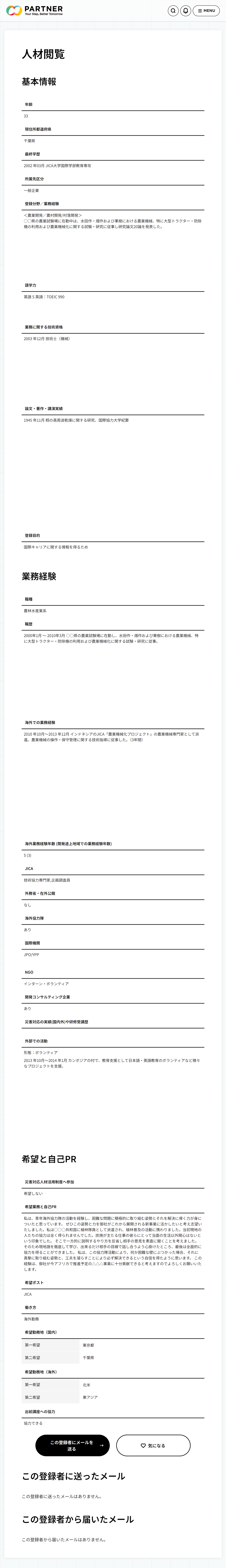第7号 連載コラム 「幸せの国」が教えてくれた国際協力
2011年3月11日午後、私はJICAブータン事務所の執務室にいた。
事務所のスタッフから「日本で何か重大な災害が起こっている」との報せを受けてテレビのスイッチを入れると、ブータン国営放送がNHKから配信された大津波の映像を映し出していた。
あの未曾有の大災害、東日本大震災である。
現場から数千キロを隔てたヒマラヤ山麓にいながら、恐ろしくも甚大な災害の状況を目の当たりにして愕然とした瞬間であった。
一夜明けた次の朝、私の携帯電話にブータン王室から一本の電話が入った。
「本日午後、国王陛下が日本と日本国民に祈りを捧げられる。至急、在留邦人に声をかけて参集いただきたい。」という内容だった。
急な連絡にもかかわらず、約70人の日本人が首都ティンプーの寺院に集まった。
国王陛下(ブータン王国第5代国王)は、寺院の祭壇に並ぶバターランプに火を灯されたあと、参集した日本人一人ひとりの手を握り、皆に見舞いと励ましの言葉をかけられた。
震災発生のすぐ翌日、しかも週末で休みのその日に、国王陛下自らが在留邦人に呼びかけ、日本国民に対する、深く、そして温かい友情の気持ちを表してくださったことに私たちはただ感動するばかりだった。
その後、ブータン王室と政府から、日本政府に対して100万ドル(当時の為替レートで約8000万円)の義援金も贈られた。100万ドルと言えば、貧しい小国・ブータンにとっては大変な金額である。この義援金について、ある省の大臣が言っていた。
「日本はこれまでブータンの発展や貧困削減のために多大な支援をしてくれた。我々には大したことはできないが、災害で困っている日本に少しでも恩返しをしたい。」
支援の手を差し伸べてくれたのは、王室や政府ばかりではない。
私の勤務するJICA事務所には、震災発生後毎日のように多くの市民が義援金を持ってやってきてくれた。中には、一枚のよれよれのお札(さつ)を握りしめ、山あいの農村から2日かけて歩いて峠を越えてやってきた老人もいた。ブータンで最高額紙幣のそのお札、日本円にして1500円ほどだが、ブータンの農民にとってはとてつもない大金である。
「昔、私の村に日本から海外協力隊員がやってきて、村の発展のために尽くしてくれた。その恩返しがしたい。今、災害で苦しんでいる日本のためにこのお金を役立ててほしい。」とその老人。
私は涙が止まらなかった。
中学生の頃、海外協力隊を描いた映画を観て国際協力の道を目指し、大学卒業後すぐにJICAに就職した。
以来30年にわたって国際協力を生業としていながら、その間ずっと、「今しているこの仕事は、本当に途上国の人々のためになっているのだろうか?」、「何のためにこの仕事はあるのだろうか?」と国際協力の「意味」や「意義」について自問し続けていた。
しかし、震災が起こったあの年のブータンでの経験で、長年の疑問にストンと答えが落ちた。
国際協力の「意味」や「意義」・・・それは決して小難しいことではなく、とてもとてもシンプルなものなのだ、ということに気づいたのだ。
国際協力とは・・・「お互いさま」ということ。
言葉を替えれば、「幸せを分かち合う」こと。
誰かが持っている幸せはほんの小さなものかも知れないけれど、皆が持っているその「なにがしかの幸せ」を分かち合う。しかも一方通行ではなく「お互いに」。
GNH(国民総幸福)政策の推進で知られるブータン。
ヒマラヤ山中の小さな「幸せの国」が、私に「国際協力とは何か」を教えてくれた。
仁田知樹
元JICA北陸センター所長