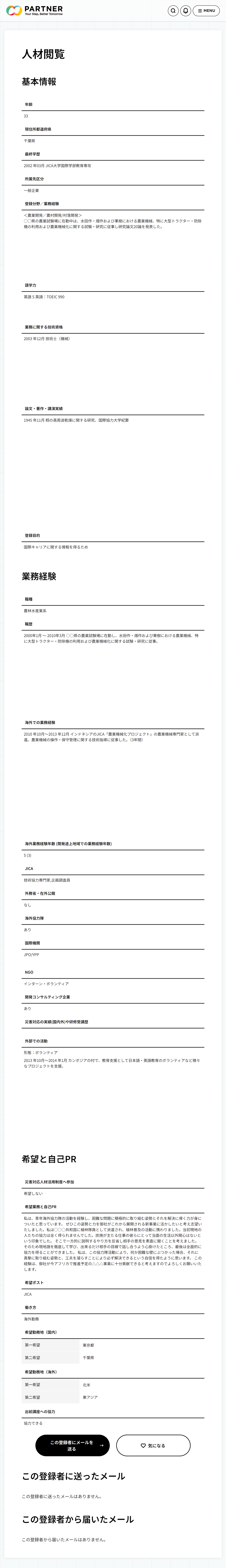第32号 PARTNERコラムブラジルの日本と日本のブラジルに魅せられて(その1)
1990年に入国管理法が変わり、南米日系人の「デカセギ」が始まりました。それまで自分がブラジルの子どもに日本語を教える先生になるなんて、ましてやブラジルに住むことになるなんて、一度も想像したことがありませんでした。
「国際学級の担当をやってみないか」と校長から打診された時、少し不安はありましたが、それでも好奇心の方が強かったです。英語はできましたが、ポルトガル語は何もわかりませんでした。
初めて国際学級で日本語を教えた日、生徒たちも緊張していましたが、私も緊張していました。ただ私が一生懸命“Bom dia”(おはよう)を繰り返していたら、彼らは笑ってくれました。緊張は徐々にほぐれ、私たちは生徒と先生というよりも「国際学級の仲間」として学びあう関係になりました。私の話すポルトガル語の多くは、その頃の生徒たちに教えてもらったものです。また、三重県には現在13,000人を超えるブラジル人が住んでいますが、当時はまだ増え始めた頃でした。
家庭訪問に行くと、お母さんたちは私にブラジルの食べ物を振舞ってくれました。「わあ。美味しい、これ!なんていうの?」「パステウ、フェイジャオン、コッシーニャ」…珍しいものばかり。
ブラジルとのポジティブな出会いは、私の人生のターニングポイントとなりました。この仕事をライフワークにしたい、そのためにはポルトガル語を話せるようになりたい、そして何より自分が「外国人」として生きるということを経験してみたくなったのです。
2000年3月、JICAの日系社会青年ボランティアとしてサンパウロ州の内陸部にある小さな町フロリダ・パウリスタに2年間派遣されました。町中の人たちが日本から来た先生を大歓迎してくださいました。聴講生として夜間学校にも入れてもらい、若い友達がたくさんできました。
バイリ(ディスコ), ナモラード(彼氏), パケラー(ナンパする)…など新しい言葉をどんどん覚えました。
ブラジルのダンスが大好きになって、リオとサルバドールのカーニバルにも出場。また、ブラジル中を旅行しました。どこに行ってもブラジルの人々は親切で、家に泊めてくれてご飯も食べさせてくれました。そして、「いつでも戻っておいで、両手を広げて待っているよ!」といつも言ってくれました。
現在の勤務校にはブラジル人児童もたくさんいます。国際理解の授業の中でこのエピソードを話すときはいつも、日本人の子どもたちは驚いていますが、ブラジルの子どもたちはにっこりと嬉しそうにしています。
(「その2」に続く)

小学校教諭
藤川純子