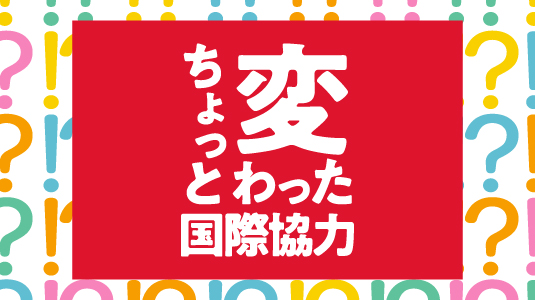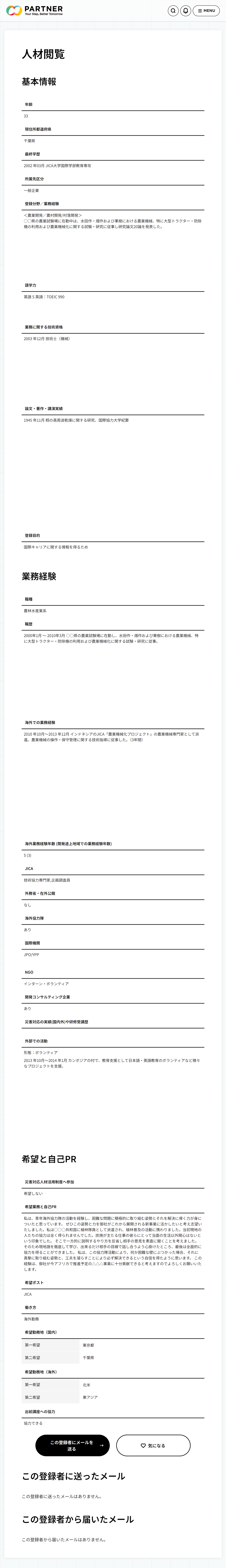第132号 PARTNERコラム
「現地の言葉で話をしたい」から始まった私の国際協力の道
高校3年生の夏、元々国際協力を仕事にしたいと思っていた私は文科省のトビタテ留学JAPANの支援を受け、バングラデシュに5週間滞在したことをきっかけに本格的に国際協力のキャリアを志すようになりました。

現在実施中のバングラデシュでの防災事業の一環として行われた
防災啓発イベントで住民の方々に話をしている様子
初めての一人での海外滞在は驚くことばかりでした。
現地に到着し、眠りについた後、明け方に鳴るアザーン(イスラム教における礼拝への呼び掛け)にびっくりして飛び起きたことを覚えています。
特に印象的だったのは、私と同い年(18歳)で結婚したばかりの子の家に泊まった時のことです。
旦那さんは仕事で家におらず、義父母と暮らしている彼女は一日中小さな家の中で家事をしながら過ごしていました。
公用語であるベンガル語は挨拶しか理解できない中、私は思わず「この生活は楽しい?」と聞き、彼女はその時の私にもわかるベンガル語で「バロ(楽しい)」と答えました。
この時、純粋に彼女のことをもっと知るためにベンガル語で話してみたいという気持ちになりました。
バングラデシュ滞在中は、首都から離れた丘陵地域にも滞在し、首都の喧騒から離れたお寺でゆったりとした時間を過ごしました。
ある日、私の面倒を見てくれていた大学生のお姉さんが、ご飯をつくってくれるお母さんやいつも話をしてくれるお坊さんが、家族を紛争で失くし、難民になった過去があることを教えてくれました。
世界にはニュースでも報道されない出来事が多くあり、人の辛さや悲しみはわかりやすいものばかりではないと知り、もっと彼ら彼女らの言葉で話を聞きたいと思いました。
その後、大学に入学し国際社会について学ぶ中でバングラデシュに難民キャンプがあることを知り、2年生の夏に初めてロヒンギャ難民キャンプを訪れました。
キャンプには、亡くなっているように見える双子の赤ちゃんを抱えたお母さんや、ビニールの屋根の下で膝を抱えながら親戚が殺害されたと話す女性など、今まで出会ったことのない状況下に置かれている人たちで溢れかえっていました。
何のスキルもないけれど、何かしなければという想いで仲間たちと難民の方々への食料支援を行うためにクラウドファンディングを行いました。
それだけではなく、やはり現地の言語を使って活動を行いたいという想いから半年後にバングラデシュ留学を決意し、帰国後は大学院でバングラデシュについてさらに学びを深めました。
現在は、いままでの経験をもとに、NGO職員として日本からバングラデシュの事業に関わっています。

留学中にベンガル語を教えていただいていた先生との写真

修士論文執筆のためバングラデシュにて学生たちに
インタビューを行っている様子
初めてバングラデシュに行ってから、今年で10年が経ちます。
今ではベンガル語で話をし、お腹を壊さずにスパイス料理が食べられるようになりました。
「現地の言葉で話がしたい」という想いで志した国際協力の道。やっとスタート地点に立ったばかりですが、これからも当時の気持ちを忘れずに精進していきます。

現在実施中のバングラデシュでの防災事業にて
村の女性に話を聞いている様子
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン
海外事業部アジア課本部担当
松本 真吏