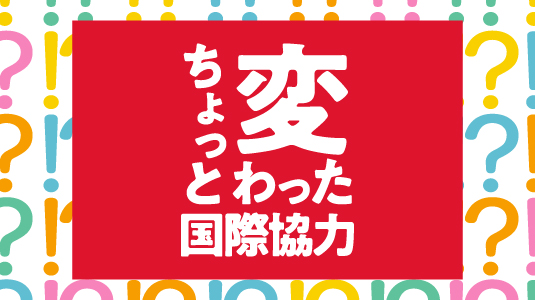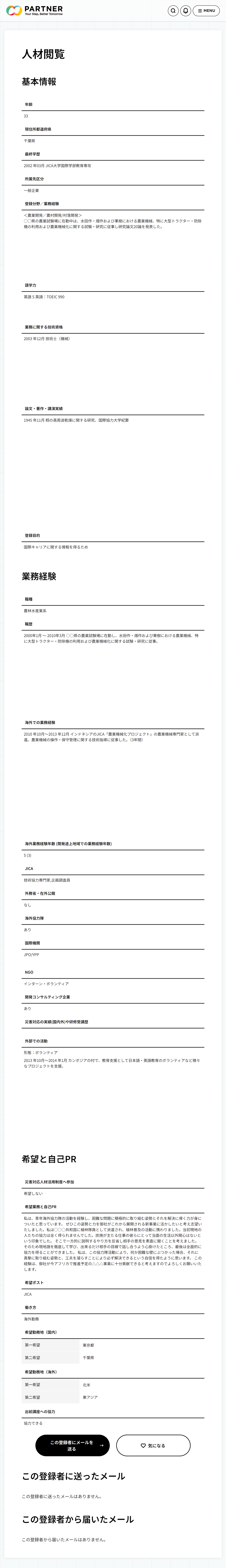第133号 PARTNERコラム
「海外だけがフィールドじゃない」
― 国際協力経験者が選んだ地域というキャリア
現在、私は長野県東部、八ヶ岳の麓にある人口約4,200人の小さな町に住み、在留外国人に関わる活動をしています。

長野県小海町(こうみまち)のシンボル松原湖から望む八ヶ岳連峰
これまで私は、JICA海外協力隊コミュニティ開発隊員としてボツワナで活動し、その後はエジプトと東ティモールのJICA事務所で企画調査員として勤務してきました。
現地の人々と共に課題に向き合う開発の現場は、刺激的でやりがいのあるものでした。
一方で、日本でも途上国からの来日者が年々増加し、地域での共生に関する課題が顕在化していることに気づきました。
そこで私は、「日本国内」を新たなフィールドと捉え、これまでの経験を活かしたいと考えるようになりました。
そして、帰国後は、難民として日本にたどり着いた方々の就労支援を行うNPOにプロボノとして参加。
母国を離れ、新天地でキャリアを再スタートさせようとする彼らと向き合う中で、私自身が海外で経験した戸惑いや葛藤が、支援の現場での共感や理解に繋がっていると感じ、NPO法人WELgeeにて、難民人材と多様な人材を受け入れたい企業とをつなぐキャリアコーディネーターとして活動を始めました。

国連が定める世界難民の日(6月20日)に関連したイベント
また、国や自治体による多文化共生施策に触れる中で、「自分自身の手で実践できる現場を持ちたい」という思いも強くなり、地域おこし協力隊を募集していた小海町に移住し、活動をしています。
まずはこの地域の状況を理解することから「地域の多文化共生推進」の活動を始めました。
小海町周辺地域は高原野菜の産地として知られ、農業に従事する外国人労働者が年々増加しています。
しかし、地域には「外国人=短期労働者」という意識が根強く、生活者・住民としての認識がまだ十分ではありません。
中長期的に定着する外国人住民が増える中で、必要な行政サービスへのアクセス支援や、地域社会の一員としての参画を促すため、自治体・地域住民・外国人それぞれに向けた啓発や交流の取り組みを進めています。

小海町高原美術館で滞在制作をする
海外アーティストによる地元小学校訪問
私自身、海外での生活の充実度は「人との出会い」によって決まっていたと感じています。同じように、日本にやってきた外国人住民の方々が地域に愛着と敬意を持ち、共に暮らしていける環境づくりが求められており、その担い手が各地で必要とされています。
異文化での生活経験や国際協力の現場で培った知見を活かせる場は、確実に広がってきていると実感しています。
長野県小海町
多文化共生の取り組み:
Facebook:地域の多文化共生@小海~共に暮らす、つながる~
Instagram:
Tabunka@小海
note(ブログ):
ともに暮らす、つながる〜地域の多文化共生@小海町〜
圓山 佐登子
2011年度3次隊 ボツワナ共和国 コミュニティ開発隊員
帰国後、企画調査員(企画)としてJICAエジプト事務所と東ティモール事務所に勤務。
2024年より長野県小海町の地域おこし協力隊として活動中。
並行して、NPO法人WELgeeにてキャリアコーディネーターとして難民人材と日本企業のマッチング支援を行う。
帰国隊員向け進路情報ページはこちら
地域おこし協力隊に関する求人も随時掲載中です(閲覧には登録が必要です)!