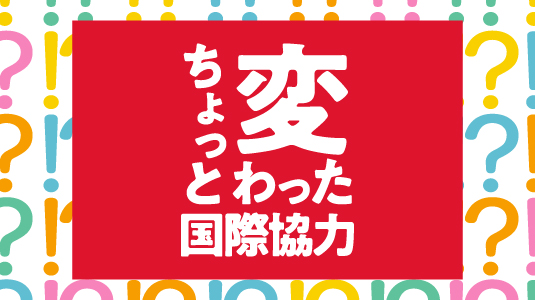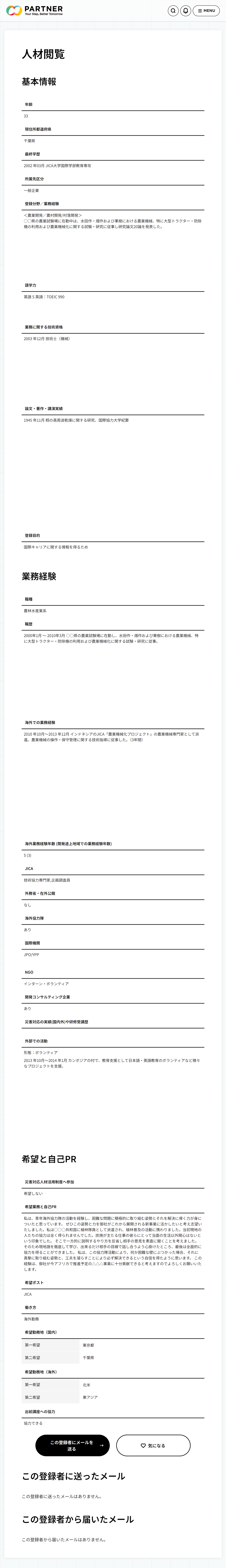第136号 PARTNERコラム
いつか、平和な故郷を一緒に見るために
バングラデシュの首都ダッカからバスで8時間。街を行き交う人々の喧騒はすっかり消え去り、しっとりと朝露に濡れた山々が広がっていました。

なだらかな山がどこまでもつづく(撮影:渋谷敦志)
バングラデシュ南東部のチッタゴン丘陵地帯を初めて訪れたのは20歳の時のこと。
日々のアルバイトで貯めたお金で航空券を買い、大学の夏休みを利用してやってきました。
この地域が持つ複雑な歴史的背景は耳にしていましたが、現地で私の心に残ったのは、人々の穏やかなまなざしと、どことなくゆったりとした時間が流れる感覚、そして自然と調和して生きる人々の姿でした。

はじめて訪れたチッタゴン丘陵地帯(右から2番目が筆者)
その後、私は行き来を重ね、ある年のジュマ正月(ジュマ:チッタゴン丘陵地帯に古くから住む先住民の人々)には20人近い同年代の友人たちと家々を訪ねて夜更けまで食卓を囲み、歌い、笑い合いました。
私はそれまで、「民族対立」や「社会課題」というレンズばかりでこの地域を見ていましたが、そこにはまず一人一人の人生や物語があるのだという、当たり前に気づかされた時間でした。

正月に川辺に集まる人々
しかし一方で、長きにわたって緊張が続いてきた地域であることも事実です。ある時、現場の最前線で活動する若い友人が、ふと漏らしたことがありました。
「僕はまだ、生まれてから平和な故郷を見たことがない」
私はその言葉を聞いて、返す言葉が見つかりませんでした。外国人である私にできることは何なのか−−。
長い時間をかけて、平和への希望を生み出す関わり方とは何だろうか。
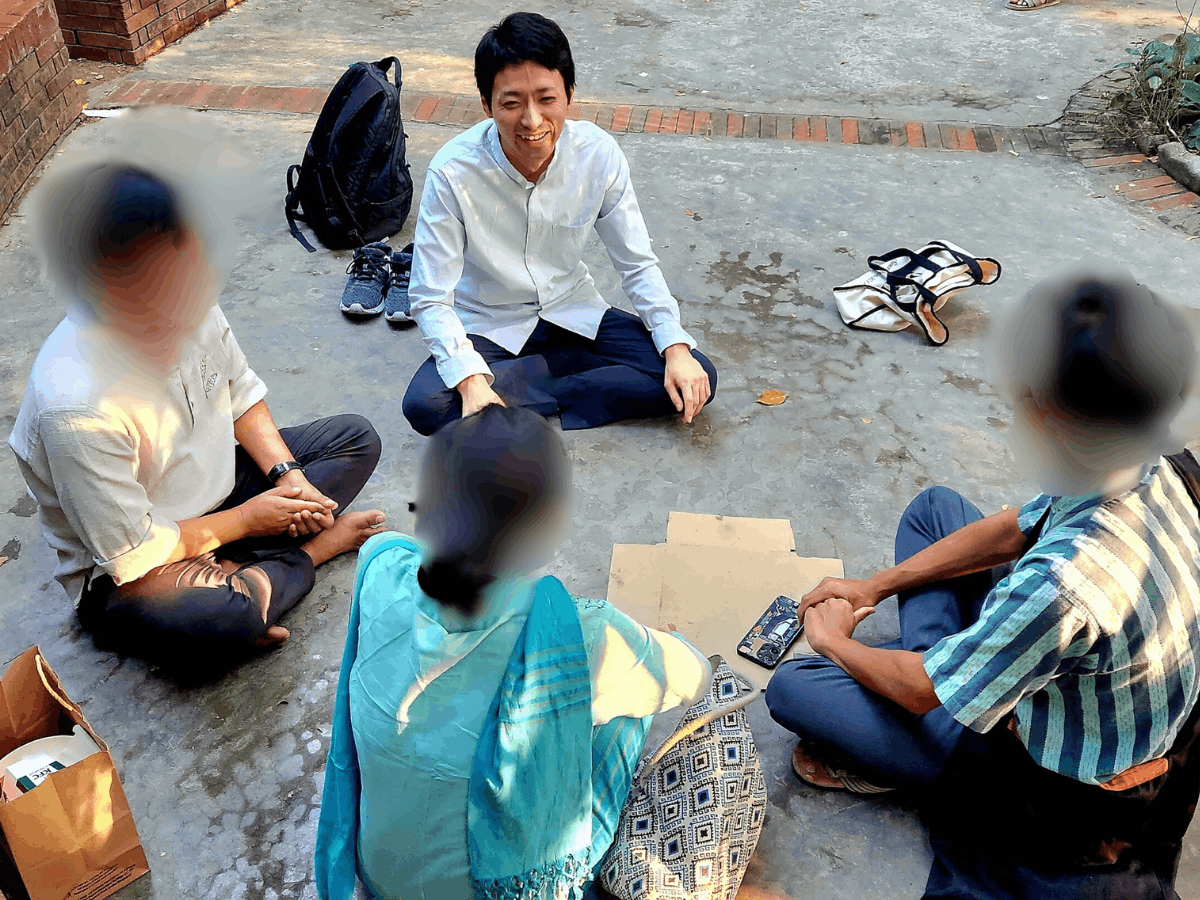
ダッカで若手リーダーたちと対話する様子
この夏、ジュマ・ネットは地域の若手リーダーや研究者、市民社会の担い手などを日本に招聘し、対話や学びを通した平和促進プログラムを実施しました。
彼も、招待したメンバーの一人でした。広島や東京を訪れ、日本が経験した戦争の記憶を受けつぎ、互いの人生を共有し、未来への希望と熱意を語り合いました。

日本の研究者や実務家との勉強会を実施した様子
平和への歩みは、数十年という単位で続いていくのだと思います。だからこそ、人と人として関係を紡ぎ、学びあい、世代を超えた争いの連鎖を超えていきます。
西日に照らされる広島の街を歩きながら、私は心に強く決めました。
「いつか、平和な故郷を一緒に見るんだ」
現地で汗を流す仲間たちと共に、一歩ずつ前に進んでいきます。

チッタゴン丘陵地帯の現状について紹介した様子
ジュマ・ネット 事務局長
稲川望
ジュマ・ネット
バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯の民族対立解決と平和促進を目的に、2002年に設立された日本の国際協力NGO