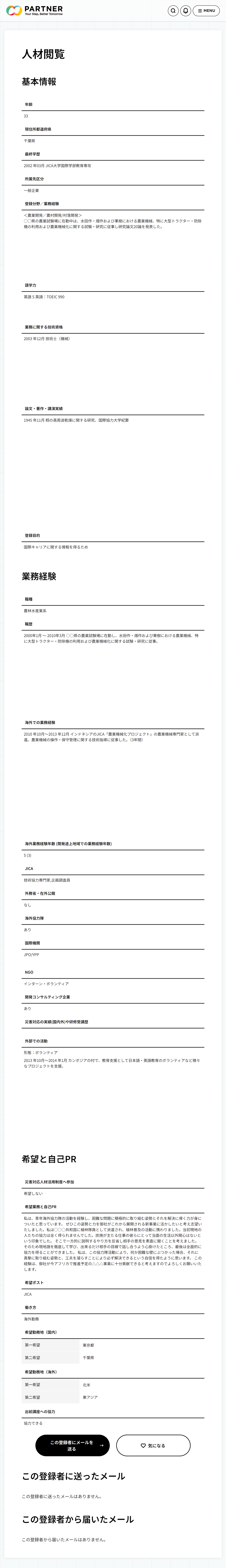登録団体詳細
認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク
団体情報
- 団体名
- 認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク
- 団体種別
- NPO法人
- 所在地
- 岩手県
- 設立年月
- 2003/ 06
- 設立目的・事業内容
- 【認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク】 20年以上前から遠野では人の魅力やその暮らしぶり、伝統文化等を活用したグリーン・ツーリズムを官民協働かつ草の根型活動として実践している。そして、その推進を担う団体として2003年度にNPO法人遠野山・里・暮らしネットワークが設立した。2005年度には山里ネットが事務局となり教育旅行を対象に農村民泊(以下:民泊)を開始した。更に近年、多くの旅番組で取り上げられるような「日常の暮らしを旅すること」へのニーズが増加とともに多様な客層が民泊を利用する流れもできている。この取り組みは、「旅行客への質の高いコンテンツ提供」「なりわいとしてのグリーン・ツーリズム」であることはもちろんのこと、「遠野に住む人がまちに誇りをもつこと」を目的にしている。 【グリーン・ツーリズムメニュー販売所 「遠野旅の産地直売所」】 地域づくりや生業づくりのためには、民泊以外の「まち」「さと」をキーワードにしたグリーン・ツーリズムコンテンツの造成が必要だった。その課題に対応するためにグリーン・ツーリズムの販売店舗「遠野旅の産地直売所」の事業を2019年9月から開始した。町場の暮らしぶりなどを体感・体験する「まちぶら」と農山村の暮らしぶりや収穫、アクティビティなどを体感・体験する「さとぶら」、農家の暮らしぶりを体感する「農家民宿」、それらを組み合わせたツアーメニューなどを販売している。
- 活動分野
- 農業開発/農村開発、経済政策、市民参加
- 活動国
- 日本
- 活動実績(国内)
- ■組織について 【岩手県遠野市とは】 岩手県遠野市(人口25,999人 2023年4月現在)は、典型的な寒冷地の中山間地域かつ盆地である。1・2・3次産業の低迷、少子高齢化、既存の観光の低迷が長年の状況である。遠野の観光は、年間170万人(うち宿泊約7万人、県内と仙台圏中心、岩手県観光統計概要より)で推移し、日帰り且つ観光施設や観光スポットを訪れるものがメインである。『遠野物語』や昔話などを代表にした「遠野らしい暮らしぶり」や四季の自然景観を求めて訪れる人が年々増えている。しかし、そのニーズに応えられていないのが観光戦略の課題である。現在、グリーン・ツーリズムがその解決策となっている。 【認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク】 20年以上前から遠野では人の魅力やその暮らしぶり、伝統文化等を活用したグリーン・ツーリズムを官民協働かつ草の根型活動として実践している。そして、その推進を担う団体として2003年度に遠野山里ネットが設立した。2005年度には山里ネットが事務局となり教育旅行を対象に農村民泊(以下:民泊)を開始した。更に近年、多くの旅番組で取り上げられるような「日常の暮らしを旅すること」へのニーズが増加とともに多様な客層が民泊を利用する流れもできている。この取り組みは、「旅行客への質の高いコンテンツ提供」「なりわいとしてのグリーン・ツーリズム」であることはもちろんのこと、「遠野に住む人がまちに誇りをもつこと」を目的にしている。 【グリーン・ツーリズムメニュー販売所 「遠野旅の産地直売所」】 地域づくりや生業づくりのためには、民泊以外の「まち」「さと」をキーワードにしたグリーン・ツーリズムコンテンツの造成が必要だった。その課題に対応するためにグリーン・ツーリズムの販売店舗「遠野旅の産地直売所」の事業を2019年9月から開始した。町場の暮らしぶりなどを体感・体験する「まちぶら」と農山村の暮らしぶりや収穫、アクティビティなどを体感・体験する「さとぶら」、農家の暮らしぶりを体感する「農家民宿」、それらを組み合わせたツアーメニューなどを販売している。 ■2011.3.11東日本大震災の被災沿岸地域への見守り活動 ~人と人をつなぎ続けるために~ 【震災当初 後方支援拠点遠野からの物資支援】 2011年の震災発生後、メールにて被災地から支援に関す状況やニーズを発信し続けたことがきっかけになり、全国150を超える団体や個人からの支援物資が集まりました。避難所は行政からの支援が届きはじめていたため、避難所に入らずに個人宅に避難している被災者へ物資を届ける活動を遠野で官民一体となって行うこととし、遠野山里ネットがその輸送の役割を担い始めました。支援物資は当初全戸対象(大槌町1,237軒、陸前高田町711軒、遠野市56軒 平成23年夏頃)にしていましたが、被災の戸別調査を同時に行いながら、徐々に要支援世帯(主に高齢者、大槌町約1,000世帯、陸前高田市約1,000世帯)へと移行していきました。また、冬季には要支援世帯を対象に灯油の支援も行いました。この活動には多くの支援金をいただきながら活動を継続できました。 【物資支援から、見守り活動、そしてコミュニティづくりへ】 その後、震災から1年が経ち、2年目に差し掛かるあたりから、物資の支援から仮設住宅への見守り活動へ移って行きます。それは、まだまだ住宅環境や就労環境、地域コミュニティの再構築が十分に行われていない現状にあったからです。被災生活で孤立しがちな方々を定期的に訪問することで「個々の生活の様子」を把握することができ、高齢者の孤独死を防ぐことに大きな効果をあげられます。また、復興公営住宅の入居により、コミュニティを新たに作る必要が出てきました。そこで、お茶っこや料理講習などを通して住民同士の交流の場づくりなども行っています。2022年頃から、個人起業支援や公営住宅の生きがいづくり、首都圏などからの三陸沿岸地域の東日本大震災スタディツアー実施、郷土芸能の保存・継承事業を継続しています。「震災前の元の暮らしに戻るまでこういった活動をしたい」というスタッフの強い思いでの活動は、同じ地域にいきる「互助」「自助」となっています。被災した方々が安心して住めるまで、このような取り組みを遠野山里ネットは継続的に実施をしていきます。
- 活動実績(海外)
- SDGsへの取り組み