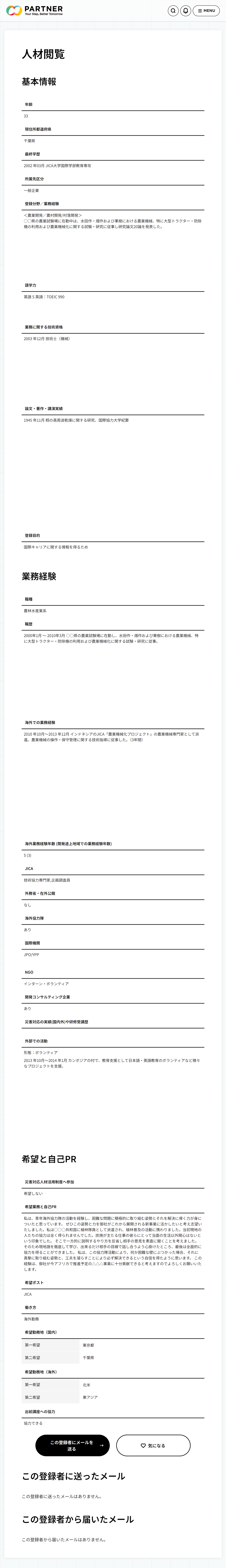登録団体詳細
特定非営利活動法人 「人間の安全保障」フォーラム
団体情報
- 団体名
- 特定非営利活動法人 「人間の安全保障」フォーラム
- 団体種別
- NPO法人
- 所在地
- 東京都
- 設立年月
- 2011/ 04
- 設立目的・事業内容
- NPO法人「人間の安全保障」フォーラム(HSF: Human Security Forum)設立の目的は以下の通りである。 人間の安全保障は、人間開発という考え方に立脚し、21 世紀の人類社会の望ましい発展 を構想するために提案された、国際社会の新しいコンセプトである。このコンセプトに基づいて、東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム(HSP:Human Security Program)は、個人の生存、 生活、尊厳を脅かすさまざまな脅威──貧困、飢饉、感染症、災害、環境破壊、紛争、組 織犯罪、薬物、人権侵害など──に対し、人間一人一人に注目しながら、新しい国際貢献 を行う人材を養成していくプログラムとして、2004 年 4 月に発足した。 そして、2011年、HSPの教員と院生の有志はさらに、既存の教育・研究分野を越え、広く公共領域における人間の安全保障に関する実践を行うために、「人間の安全保障」フォーラム(HSF:Human Security Forum)を設立した。このフォーラムは、日本、アジア、アフリカその他の地域の持続的平和と持続的開発を追求し、移民や難民、災害などによる被災者をはじめしばしば脆弱な立場におかれる人々の基本的人権が尊重される社会を実現することを目指し、人間の安全保障に関心をもつ関連組織、企業、官公署、自治体、団体、ならびに個人と恊働・協力しつつ、日本国憲法の理念にも通じる人間の安全保障推進事業を行う。これにより、すべての人の命、生活、尊厳を守り、持続可能で、公正な社会発展に向けて、わが国が世界に先駆けて人間の安全保障の体制を推進・確立していくことに寄与する。 2010年4月より設立準備を開始するも、予定していた設立総会(2011年4月2日)の直前に東日本大震災が発生。まずは任意団体として震災復興支援活動を開始した。まず東京〜宮城間でのウィークエンドボランティア派遣事業を5月から実施し、10月までで16回の派遣を行った。そして、2011年9月9日に内閣府より認証を受け、2011年10月31日にNPO法人化を果たした。 そして、2010年11月以降は、宮城県登米市に支援の拠点となるHSF東北出張所を設置し、2012年7月現在まで、宮城県三陸地方(気仙沼市、南三陸町、石巻市)出身の被災した子どものための教育支援(「こども未来館」プロジェクト)を行っている。その主な活動内容は、仮設住宅団地において、子どもの学び、遊び、育ちの場づくりのために、学童保育や学習指導、様々な文化的イベントの実施である。この支援活動においては、HSFスタッフだけでなく現地の行政、大学、NPO、ボランティアと連携しながら、活動の規模や実施範囲を広げ、長期継続できる支援体制づくりに取り組んでいる。また、東北の震災復興支援だけでなく、東京都内で国際協力に関するシンポジウムやサマースクールなど様々なイベントも開催している。初代理事長は、現国連事務次長の高須幸雄。
- 活動分野
- 貧困削減、教育、都市開発・地域開発、平和構築、援助アプローチ/戦略/手法
- 活動国
- 日本
- 活動実績(国内)
- まず、設立と同時に取り組んできた3.11以降の東北復興支援には以下のようなものがある。 ①ウィークエンド・ボランティア 2011年3月11日に発生した東日本大震災被災地における最初の活動として、HSFは持続可能な支援の鍵として、できる範囲で協力したいという市民のための選択肢を用意することを目的に「ウィークエンド・ボランティア」を開始した。金曜日の夕方に東京大学駒場キャンパスを1BOXカーで出発し、その日の夜にHSFの仙台の宿舎に到着。そして、土曜日1日と日曜日の半日をボランティア活動に費やし、日曜日の夜に東京に帰還、という流れである。また、その際、ボランティア保険の代行加入や、ボランティアに必要な準備もHSFで用意し、「身体一つで参加できるボランティア」がキーワードとなっていた。これは、平日に仕事や学業で十分に時間がとれない社会人や学生をターゲットにしたもので、そうした人々のニーズに合致したものだったといえる。この事業は2011年10月まで継続し、述べ16回の派遣を行った。 ②「こども未来館」プロジェクト 多くの被災地域において、慣れ親しんだ居住空間を失った人々は現在、仮設住宅や代替宿舎での生活を余儀なくされている。そうした住宅居住者の中には、当然、子どもや若者も多く含まれている。物質的にも精神的にも満たされない環境で育つ子どもは、被災者の中でも特別なケアを必要とする脆弱な存在である。しかし、旧知の仲でもない人々が抽選によってあてがわれた住居で隣り合わせに暮らす仮設住宅地において、コミュニティで子どもを育てる、という隣人同士の信頼を基盤とする取り組みはより困難となる。また、財産を失った家庭にとって、子どもの進学や就職の問題は、今後増々深刻化していくことが予想される。 そこで、HSFは、2011年11月より宮城県内の仮設住宅団地において、被災した子どもの学び、遊び、育ちの場となるような「こども未来館」の設置に着手した。「こども未来館」では、子どもや若者の進路相談や学童保育/学習指導を行うボランティアが配置され、さらに様々な文化的イベントも定期的に開催している。こうした諸活動を通じて、被災した子どもや若者が自信、誇り、未来への希望を抱けるような空間を創出し、仮設住宅 地における明るい活気あるコミュニティの発展に貢献する。2012年7月現在、宮城県登米市、南三陸町、気仙沼市、石巻市でこのような教育支援を展開中である。 ③東京都内の市民向け復興支援チャリティ・イベント これまで、東京大学駒場キャンパス内においてピアノ・チャリティ・コンサートを2回行った。 ・2011年4月2日「人間の安全保障」フォーラム設立記念コンサート 演奏者:大江博(在パキスタン特命全権大使) ・2011年10月8日「人間の安全保障」と東日本大震災シンポジウムとコンサート 演奏者:平原誠之(ピアニスト) さらにHSFは、東日本大震災の被災地における復興支援活動と平行して、東京大学寄付講座「難民移民(法学館)」難民移民ドキュメンテーションセンター(CDR:Center for Documentation of Refugees and Migrants)と協力し、市民向けの短期集中型アカデミック・コースワークや、国際協力に関するイベントを東京大学駒場キャンパスにおいて開催した。 ④CDR−HSFスペシャルサマースクール2011『国際法における難民の権利』 ミシガン大学のジェイムス・C・ハサウェイ教授を講師に招き、2011年に9月27〜29日の3日間に渡って開催された。この市民向けアカデミック・コースワークは、難民保護の重要課題に関する理論と知識を受講生と共有することを目的とし、約50名の学生と一般の参加者が集まった。そして、規定数の講義を受け、その内容に関する論文を提出した受講生には、CDR代表とHSF理事長の連名による修了書が発行された。 ⑤国際協力インターンの集い2011秋 2011年12月7日に開催されたこのイベントは講演会(前半)と交流会(後半)の二部構成で、参加者に対して国際協力インターンに関する知識と実際にインターン先を見つける機会の両方を提供することを目標としていた。第一部の講演会では、「国連と企業とインターン」をテーマに国連プロジェクトサービス機関(UNOPS:United Nations Office for Project Service)山本芳幸氏の講演が行われた。第二部の交流会では、インターンを必要とする国際機関やNPO、企業の関係者とインターンを希望する参加者、およそ150名により自由な雰囲気の中で交流が行われた。
- 活動実績(海外)
- SDGsへの取り組み