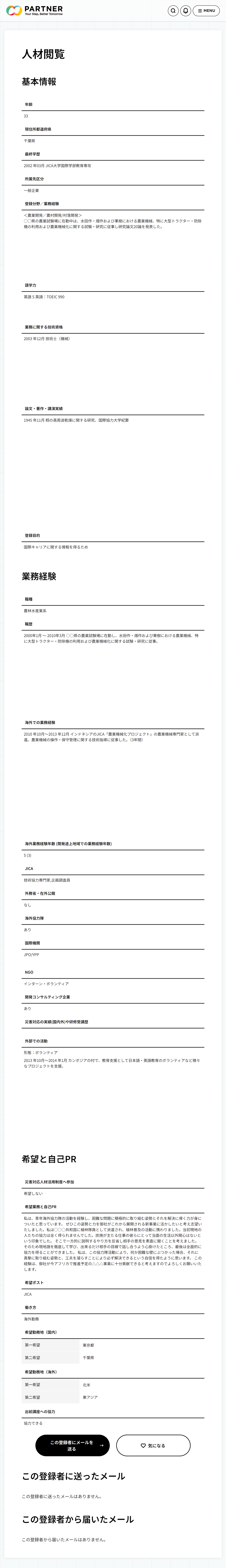登録団体詳細
特定非営利活動法人 日本下水文化研究会
団体情報
- 団体名
- 特定非営利活動法人 日本下水文化研究会
- 団体種別
- NPO法人
- 所在地
- 東京都
- 設立年月
- 1992/ 04
- 設立目的・事業内容
- 人の生存基盤を維持していくうえで欠かせない水資源を安定的に確保し、安全に供給することは、多くの地域で緊急の課題となっている。うるおいのある清らかな水環境を守り、次世代もまたその恩恵を享受できるようにしていくためには、市民ひとりひとりが水環境問題を自分の問題として捉え、責任ある行動をとることが求められる。すなわち、個人や社会と水との付き合い方の成熟が必要である。成熟した水との付き合い方を「水文化」と呼ぶことができるが、そのなかで排水行為に注目した人と水との関わりのあり方を提示していくことを目指す。 下水文化は長い歴史を持ち、賢い水の使い方や水を汚さない知恵として生活のなかに息づいてきた。しかし、近代化の過程で、家庭で使われ汚れた水や都市に降った雨水を厄介なものとして扱い、できるだけ速やかに遠くへ、そして目に見えないように持ち去ろうとしてきたことは、下水が流れた先で何が起きているのかを想像する感性を人々から奪ってしまった。今日では、下水を受け入れ処理をするということが、技術的に高度化し、専門家任せとなり、下水文化は忘れ去られてしまっている。そして、物理的な水循環ばかりでなく、私たちと水とのこころ豊かな関係も断ち切られている。 下水文化を再発掘し、そこから何を継承するのかを明らかにし、新たな問題意識のもとで、水の使い方、使った水への配慮を含めた水との付き合い方を基本とした水循環社会の形成が、今望まれている。水との豊かな関係性を育む生活は、私たちと水との関係を再び近づけてくれる。「下水」から目を逸らさずに直視すること無しには、水環境・都市環境再生の展望は開かれない。下水文化は、人間を含め、すべての生き物たちに欠かせない「生命(いのち)の水」を次世代に継承する要諦となる。 開発途上国においては、以上の趣旨にのっとり、生命と水資源を脅かす屎尿の衛生的管理の普及を目指す。このため、それぞれの地域にふさわしい技術の導入、それを自立的に支える社会システムの確立を目的とした活動を行う。その結果として、安全な飲料水源の確保、屎尿資源の循環利用、健康リスクの減少、貧困削減を図る。 日本下水文化研究会は、地球上の人々の生命と掛け替えのない水環境を守るため、今日的な水との付き合い方を創造し、水管理の成熟と水文化の発展に寄与することを目的とする次のNPO活動を行い、その成果を国内外へ発信する。 ①境教育の推進を図る活動、②下水文化の調査研究を行い、普及啓発を図る活動、 ③環境の保全を図る活動、④国際協力活動 以上の目的を達成するため、下水文化に関する調査研究をおこなうとともに、普及啓発、政策提言のため、研究会、見学会、研究発表会を開催し、これらの成果を図書として発行している。これまで、下水文化研究発表会を12回、シンポジウム・フォーラムを5回開催、機関誌「下水文化研究」第1号~第25号(1992年の設立前を含む)、9冊の下水文化叢書を発行した。
- 活動分野
- 農業開発/農村開発、保健医療、都市開発・地域開発、環境管理、水資源、防災
- 活動国
- バングラデシュ
- 活動実績(国内)
- 国内活動としては、事業内容に述べた定期刊行物の出版活動のほか、以下の活動を行ってきた。 ・ 我が国「衛生工学の父」W. K. バルトンの業績を広く伝搬するため、8月5日のバルトンの命日には、バルトン忌を開催し、バルトンの功績に関する新たな発見等に関する講演会を開催している。2006年、2009年には、その功績を故国スコットランドに伝えるため、スコットランドで記念事業をスコットランド側委員会とともに実施した。 ・ 全国の下水道博物館の活性化を意図して、「交流会議」を支援してきた。交流会議は、現在では中断しているため、下水道博物館実態調査を行い、その結果と活性化を促すアピール文を関係諸機関に提出した。 ・ 東京都の水源林をもつ山梨県丹波山村、小菅村との上下流交流。 ・ 経営・管理の時代を迎えている下水管理に関する出前講座の企画、募集。 ・ 三大地震写真集(濃尾、関東、阪神・淡路)を発行(1996年)。
- 活動実績(海外)
- 本会では、地球環境基金の助成を受け、2004年度より3ヵ年にわたり、「バングラデシュ農村地域における衛生改善のための普及啓発活動」を実施した。このなかで、政府機関、ローカルNGOとの協働のもと、40基のエコサン・トイレ(エコロジカル・サニテーションの概念を具体化し、屎と尿の分離を行い、衛生機能を改善するとともに、屎尿を資源として活用することを意図したトイレ)を導入した。尿が肥料効果を有すること、乾燥した便が化学肥料で疲弊した農地の土壌改良に寄与することを確かめた。エコサン・トイレは、技術的にも社会的にもバングラデシュの農村社会に受け入れられたということができる。この成果を受け、JICA草の根技術協力(協力支援型)およびTOTO水環境基金の助成により、より広い地域で活動を展開し、導入トイレ基数を増やした(JICA、 TOTOのプロジェクトはいずれも2007年10月より2年間実施)。農村のトイレと言えば、ピットラトリン以外の選択肢がなかったバングラデシュにおいて、申請団体の活動を契機としてエコサン・トイレが認知され、複数のNGOが普及活動を行っているほか、バングラデシュ政府が全国的な普及プロジェクトの実施を試み、UNICEFも地域特性の異なる複数のサイトで導入プロジェクトを実施している。さらに、2010年度より、JICA草の根技術協力事業(パートナー型)に採択され、エコサン・トイレの地域コミュニティによる自立的管理、地域衛生管理、そのためのコミュニティベースの組織設立、普及拡大に向けた建設・維持管理マニュアルの作成、全国的なエコサン・トイレに関する情報収集システムの開発などの活動を行った。2013年度から、JICA草の根技術協力事業(パートナー型)が継続採択され、リボルビングファンドによるエコサン・トイレの普及拡大ならびにエコサン・プロダクトである乾燥便の販売等の活動展開を行っている。 本会がエコサン・トイレを導入した理由として、上記の屎尿の農業利用のほかに、洪水常襲地域の広がるバングラデシュにおいて、既存のトイレの多くが洪水期に使用できず、衛生状況が悪化することから、洪水時にも使用可能なトイレが必要であること、井戸水の砒素汚染地域において、汚染した井戸水に代わる飲料水源となり得るため池などの表流水が、現状の屎尿管理のもとでは汚染リスクが高いことがあげられる。三井物産環境基金により採択された「バングラデシュ農村地域での水と衛生に関わる生活改善活動」(2008-2009度)は後者の理由から提案したものであり、所期の目的を達成した。このプロジェクトサイトの村では、2011年の洪水期において、特性の類似する他の村に比べて下痢症患者が圧倒的に少なかったことが確かめられている。 2012年度より、より深刻な生活環境下にある都市スラムにおける衛生改善プロジェクトを地球環境基金の助成を受けて実施中であり、適用技術としては、汚泥処理インフラをもたない都市において、環境インパクトをできるだけ削減すること、資源利用が図り、スラム住民に衛生改善のインセンティブを高める意図から、バイオガス反応槽を選択した。現在では、発生したバイオガスは5世帯の台所の燃料として用いられ、徴収した料金はトイレ清掃費(清掃人の雇用)に充てられている。 こうした成果を伝搬するため、日本国内では、本会が主催している研究発表会(2003年、2007年、2011年)において、開発途上国の衛生問題や海外協力事業におけるNGOの役割などについて議論した。国際衛生年の2008年12月には、JICA地球ひろばと共催で「水と衛生に関わる開発援助」フォーラムを開催し、開発途上国の衛生改善に関し議論を行った。得られた成果は日本語、英語の報告書を作成し、研究論文等としても内外で公表しており、2006年度には京都大学環境衛生工学研究会より、優秀プロジェクト賞を受賞した。 このほか、2012年度日本水フォーラムが主催した「世界のトイレプロジェクト」において、エコサン・トイレの普及活動において、「優れた取組み賞」を受賞し、賞金ならびに活動支援費を得た。この活動支援費をもとに、ソーシャル・ビジネスによる衛生的なトイレの普及を図るための事業に着手している。
- SDGsへの取り組み