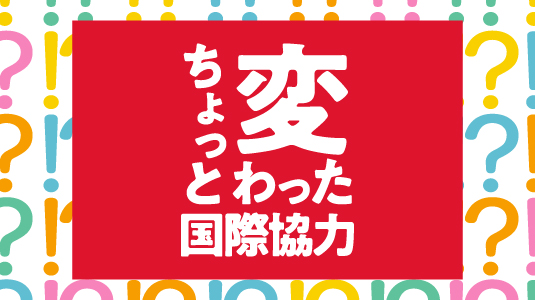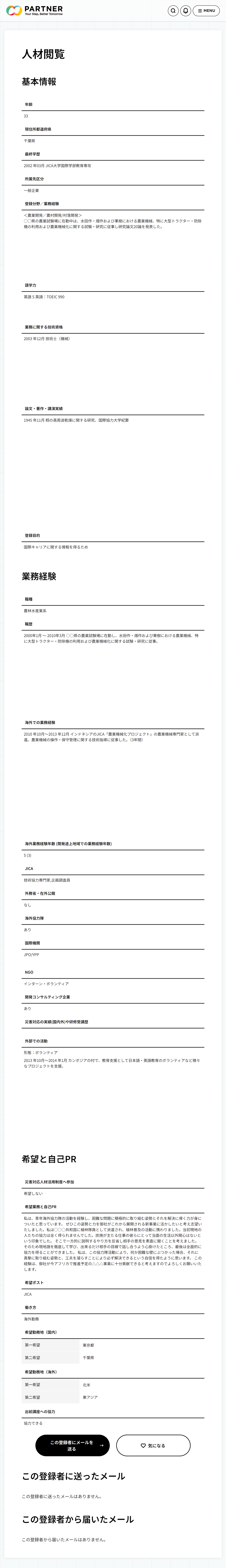いつもの買い物が世界を変える!?
美味しい!かわいい!フェアトレード商品の魅力を探る!

「国際協力」と聞くと、大きなプロジェクトや遠い国を思い浮かべがち。ですが、実は私たちの「買い物」でも、世界の誰かをサポートできるとしたら、ちょっと面白いと思いませんか?
普段の生活のなかで、それを実現するのが「フェアトレード」。実は、単なる支援や寄付ではなく、生産者と対等なパートナーシップを生み出す仕組みなのです。
本記事では、そのフェアトレードをさらに進化させた「コミュニティトレード」を掲げる株式会社プレス・オールターナティブを取材。カレーの壺シリーズや伝統工芸の刺繍雑貨など、魅力的な商品に詰まった「共にハッピーになる」考え方を紹介します。
Vol.1では、フェアトレードの基本や実際の商品例を中心に紹介!次回Vol.2では、生産現場のリアルなストーリーに迫ります。
まずは「買う」ことで始められる国際協力の新しいカタチを、一緒にのぞいてみましょう!
はじめに知っておきたい、フェアトレードの概念
「フェアトレード(Fair Trade)」とは、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいいます。(出典:
フェアトレードの定義|FAIRTRADE JAPAN
)
日本では「途上国を助ける慈善活動」という印象を抱かれがちですが、実際はもっとフラットな関係づくりがポイントです。
たとえばコーヒーやチョコレートで見かけるフェアトレード認証マーク。その背景には、生産者が技術やアイデアを活かしながら、買い手と一緒に新しいものを生み出している仕組みがあります。
今回取材した株式会社プレス・オールターナティブでは、このフェアトレードをさらに発展させた「コミュニティトレード」という考え方を掲げています。
自社で展開する「第3世界ショップ」の成り立ちや、商品づくりの裏側などを、営業マネージャーの山﨑さんに伺いました。
スリランカのスパイス工場やインドの伝統工芸プロジェクトなど、現地の生産者と対等な関係を築きながら、持続可能な事業モデルを展開。
単なる貿易にとどまらず、地域課題の解決にも積極的に取り組んでおり、フェアトレードの新たな可能性を切り開いている。
営業活動で商品の魅力を広めるだけでなく、現地生産者の訪問や、フェアトレードの意義を伝える講演、商品を使ったレシピ開発など、多岐にわたる活動を展開している。
(こちらもオススメ!)生産者とのやり取りや文化の違いを乗り越える方法など深堀りした記事: 『フェアトレードの現場をのぞいてみよう!「特別な支援」ではなく、一緒に続けるビジネスのかたち』
プレス・オールターナティブが掲げる「コミュニティトレード」が生み出す、対等なパートナー関係
――今日はお時間をいただき、ありがとうございます!まずは会社の事業と、山﨑さんの簡単な経歴について伺えますか?
山﨑さん:
弊社は1985年に創業しましたが、当初はまだ事業の形がはっきりしていませんでした。
ただ、「社会的な課題を解決することをビジネスにしたい」という思いがあり、1986年からフェアトレード事業を始めています。
私は大学時代にインターンシップで関わり、そのまま入社。当時は女性の開業支援などを行っていましたが、入社後すぐに輸入・販売部門である「第3世界ショップ」の担当になり、気づけば20年以上ずっとこの会社にいます。

――新卒からずっと担当されているんですね! 御社が行っている「フェアトレード」ですが、支援や寄付というイメージを持つ人も多い気がします。実際はどんな取り組みなのでしょうか?
山﨑さん:
日本だと「途上国を助ける」というイメージが強いですが、私たちは「支援」というより「対等なパートナー関係」を大切にしています。
生産者さんに「これ作ってよ」と一方的にお願いするのではなく、お互いに「こんなことできる?」「こういう想いがある」と率直に伝え合い、商品を生み出していく。
そんな「コミュニティトレード」の関係が、私たちの軸なんです。

山﨑さんが生産者さんとお話されている写真
かわいい&実用的!「第3世界ショップ」で買える、フェアトレード商品の魅力
――具体的な商品について伺いたいです。「第3世界ショップ」では、どんな商品を取り扱っているのでしょう?
山﨑さん:
大きく分けると、食品系とハンドクラフト系があります。
食品だとコーヒーや紅茶、チョコレート、ドライフルーツなど普段の暮らしに取り入れやすいものが中心です。

「第3世界ショップ」で取り扱っている商品の一部
中でも人気なのが、スリランカの高品質スパイスをペーストにした「カレーの壺ペースト」。「これを入れるだけで本格的な味になる」とリピーターさんが多い商品ですね。
もともとはスパイスセットをそのまま輸出していましたが、「日本人がもっと手軽に作れるように」というアイデアからペースト化し、スリランカの家庭の味をベースに日本人好みの辛さや味に調整しているのがポイントです。

左がスパイスセット。右がお手軽ペーストタイプ。
簡単に本格的なスリランカカレーが作れる
――確かに、とても便利そうですね! ハンドクラフト系はどんなものがありますか?
山﨑さん:
たとえば「ミラー刺繍」や「山羊革工芸」など、インドの伝統技術を活かした雑貨ですね。
ミラー刺繍のポーチはカラフルで可愛らしく、山羊革の小物は使い込むほど味が出る風合いが魅力です。
どちらも手作業ゆえに大量生産が難しいですが、購入することで現地の雇用や技術継承を支えることにもなるんですよ。
もちろん他にも、ペルーのアルパカニット製品をはじめ、色々な国の工芸品がそろっているので、見ているだけでも楽しいと思います。

ミラー刺繍製品

山羊革工芸品
――どれもオシャレで実用的ですね。カレーの壺シリーズは手軽にスパイス料理が楽しめそうですし、雑貨はデザイン性も高くて惹かれます。
山﨑さん:
はい。まずは「可愛い・美味しそう・使いやすい」というような、商品そのものの魅力で選んでもらえたら嬉しいです。
しかもフェアトレード商品は、買うこと自体が生産者支援につながったり、作り手のことが見えるのが大きな魅力です。
ここでは簡単に商品を紹介しましたが、Vol.2ではスリランカの工場やインドの刺繍工房がどんなふうに変化を遂げてきたか、より深いストーリーをお話しできると思います。

商品の魅力を語る山﨑さん
フェアトレード商品は「高い」?見える情報には理由があった
――フェアトレードの商品は、スーパーやコンビニで買える大量生産品より割高という印象を受けることがあります。なぜそうした価格差が生まれるのでしょうか?
山﨑さん:
「ちょっと高い」と思う人がいるのは確かかもしれません。
でも、その価格には「生産者が無理なく続けられる環境」を整えるコストが含まれているんです。
たとえば、私たちが取引しているスリランカのスパイス工場では、社員寮を整備して光熱費を無料にしたり、障がいのある方の雇用を進めたり、農家さんには有機栽培を指導して銀行融資を手伝ったり。
そうした「長く続ける仕組み」にはどうしても投資が必要なんですね。

スリランカのスパイス工場のワーカーと従業員宿舎
逆に、価格があまりに安すぎるものには必ず理由があると思います。
誰かが無理をしていたり、適正な対価が支払われていなかったりする可能性もあるかもしれません。
ちょっと高めに見えても「何に手間やコストをかけているんだろう?」と考えるだけでも、納得できることが多いんですよ。
――なるほど。あと「フェアトレードは流通が不安定」と耳にしたことがありますが、そちらの苦労はありますか?
山﨑さん:
ハンドメイド雑貨は大量生産が難しいので、オーダー数を確保したり納期調整したりと工夫は必要ですね。
でもカレーの壺シリーズを作っているスリランカの工場のように、ラインが整備されてまとまった量を作れる例もあります。
生産者の得意分野に合わせて、「大量生産できる所には多めに」「手仕事中心の所には無理なく」というふうにフレキシブルに依頼しているんです。
また、フェアトレード商品だからといって流通が特別遅れるわけではありません。
むしろ生産者と顔が見える関係でフォローし合える分、トラブルが起きた際に対応しやすい面もあるんですよ。
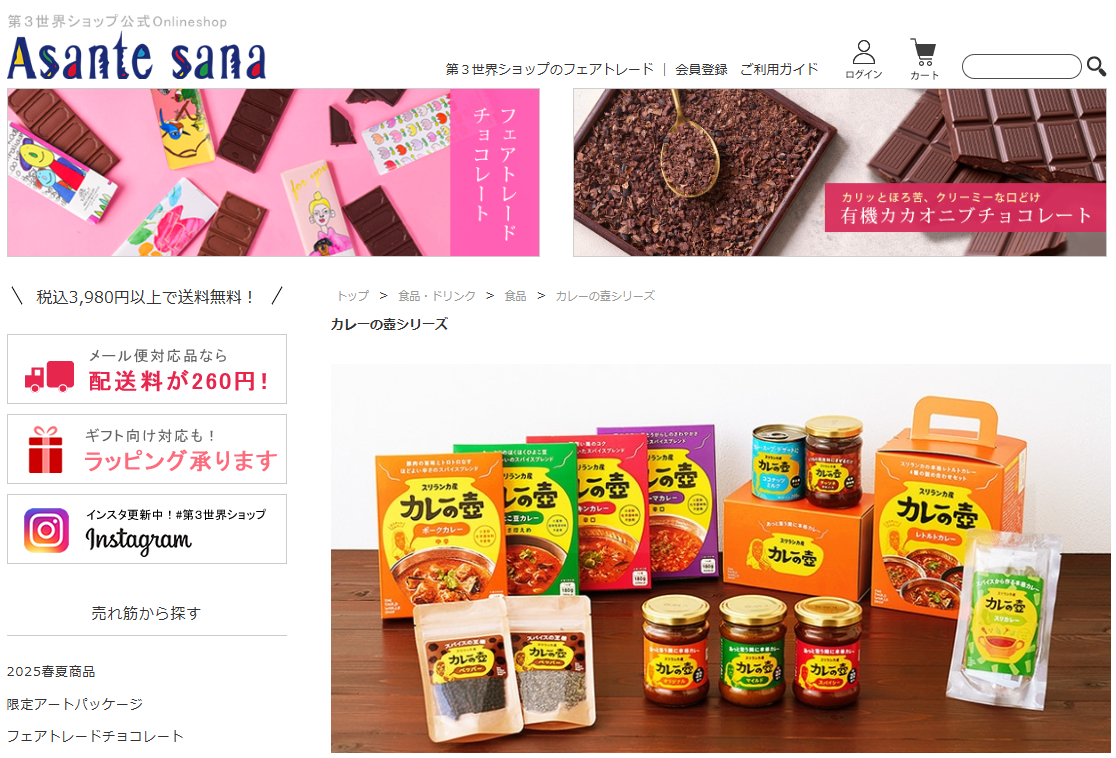
公式通販サイト「
アサンテ サーナ
」
では、たくさんの商品を取り扱っている
まずは気軽に。フェアトレード商品はどこで買える?最初に選ぶとしたら何?
――身近な場所でフェアトレード商品を買えるところはありますか? また、初心者へのおすすめはありますか?
山﨑さん:
コンビニやスーパーでもフェアトレード認証のコーヒーやチョコは見かけるようになりましたし、大手のカフェチェーンでも手に入ります。弊社の商品なら、生協や自然食品店などで購入できますよ。
最初に何を買えばいいか迷ったら、普段の買い物と同じように「自分が好きなもの」から始めてみてください。カレー好きなら「カレーの壺」、雑貨好きならミラー刺繍や革工芸を…といった感じですね。
フェアトレード専門店やセレクトショップで新しい商品を探してみるのも面白いですよ。
――確かに、まずは気軽に手に取るところからですね!
山﨑さん:
はい。私たちも「大々的にフェアトレードをアピール」するより、「興味を持った人一人ひとりに丁寧に伝える」姿勢を重視していますし、都内の雑貨店で取り扱っている商品もあるので、気軽に試してほしいです。
人気商品であるチョコレート「Artisanシリーズ」の可愛らしいアートを使ったパッケージも、そんな「手にとってもらえる機会」を増やす工夫の1つです。

神奈川・平塚にある福祉施設/アトリエの
「嬉々!!CREATIVE」のアーティストたちが
パッケージを手がける「Artisanシリーズ」は、
雑貨屋などでも購入できる
実はパッケージの裏側には、このチョコレートに関わる産地や生産者のエピソードが書かれているんです。
「可愛い」 「美味しそう」 「面白そう」と直感で選んでみて、あとから「これってフェアトレードだったんだ」と気づいてもらえるのも、1つの形としていいなと思っています。
公式サイトやSNSでも、生産者のストーリーやレシピを紹介しているので、もっと知りたくなったらぜひのぞいてみてください。

「Artisanシリーズ」のパッケージ中面。
カカオ豆を作る生産者さんや、
おいしさへのこだわりを紹介している
編集者より
「フェアトレード=支援」という先入観を持つ方も少なくありませんが、プレス・オールターナティブが目指すのは生産者と対等に意見を交わし合い、お互いがハッピーになれる関係をつくることだと感じました。
そこから生まれるカレーの壺シリーズや可愛い雑貨には、言い尽くせないほど多様なストーリーが詰まっていますね。
「フェアトレード商品を買う」それは国際協力をより身近に感じさせる新しい視点だと思いました。そして、その視点は私たちの生活をちょっと豊かにしてくれるものなのかもしれません。
本記事Vol.1では、フェアトレードやコミュニティトレードの基本、そして「どんな商品があるのか」をご紹介しました。次回Vol.2では、実際にスパイス工場や刺繍工房でどのような変化が起きているのかなど、より深いドラマに迫ります。
フェアトレード記事 Vol.2はこちら
☆生産者とのやり取りや文化の違いを乗り越える方法を深堀りした記事はこちら♪