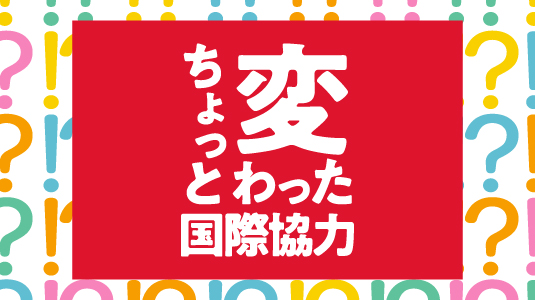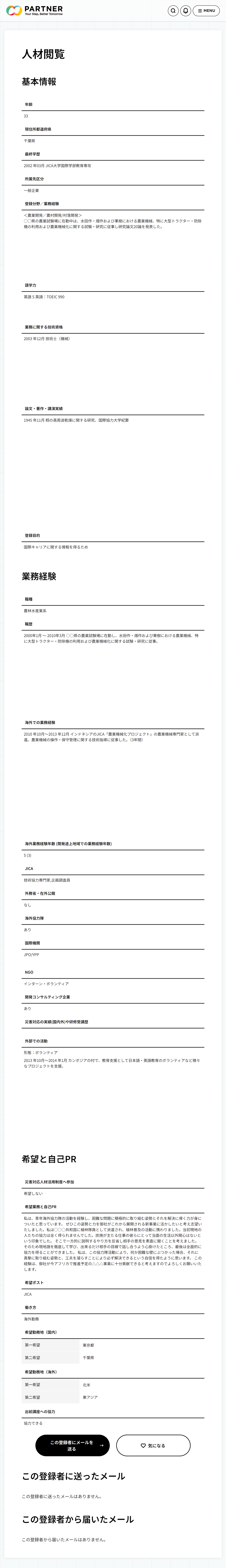フェアトレードの現場をのぞいてみよう!
「特別な支援」ではなく、一緒に続けるビジネスのかたち

Vol.1では、フェアトレードをさらに発展させた「コミュニティトレード」を掲げる株式会社プレス・オールターナティブの基本的な取り組みや商品の魅力を中心にお届けしました。
Vol.2はその背景を、さらに掘り下げます。
営業マネージャー・山﨑さんへのインタビューを通じて、生産者とのやり取りや文化の違いを乗り越える方法、そして実際にどんな変化が起きているのか――「フェアトレードの現場」をじっくり伺いました。
スリランカのスパイス工場やインドの伝統工芸プロジェクトなど、現地の生産者と対等な関係を築きながら、持続可能な事業モデルを展開。
単なる貿易にとどまらず、地域課題の解決にも積極的に取り組んでおり、フェアトレードの新たな可能性を切り開いている。
営業活動で商品の魅力を広めるだけでなく、現地生産者の訪問や、フェアトレードの意義を伝える講演、商品を使ったレシピ開発など、多岐にわたる活動を展開している。
(こちらもオススメ!)フェアトレードの基本や実際のフェアトレード商品について紹介した記事: 『いつもの買い物が世界を変える!?美味しい!かわいい!フェアトレード商品の魅力を探る!』
最初は「まったく知らなかった」。山﨑さんが、フェアトレード業界に入ったきっかけ
――山﨑さんは新卒からプレス・オールターナティブにいらっしゃると伺いました。もともと、フェアトレードや国際協力に興味があったのでしょうか?
山﨑さん:
いえ、実はまったく知りませんでしたし、興味もなかったんです(笑)。
私は山口県の大学に通っていたのですが、プレス・オールターナティブ創業者の片岡が「地域の問題解決」に関する講義をしていまして。
そこでの内容は「自分たちでやってみることが大事だ」、「起業して地域の課題に取り組むことも選択肢のひとつだ」ということでしたね。

――なるほど。いつ頃からフェアトレードに関わるようになったのでしょう?
山﨑さん:
実は、入社してからなんですよ。
大学時代に、プレス・オールターナティブのインターンへ友人が参加していて、一緒について行ったんです。
そして入社する少し前に「第3世界ショップの担当だよ」と言われ、そのままフェアトレードに携わることに(笑)。
英語も得意じゃないし、国際協力やフェアトレードの知識なんてほとんどない状態でしたが、働いてみると、ニーズや状況に合わせた柔軟な対応を重視する社風に驚きつつも、やりたいことに挑戦できる風土に惹かれ、気づけば20年以上続けています。
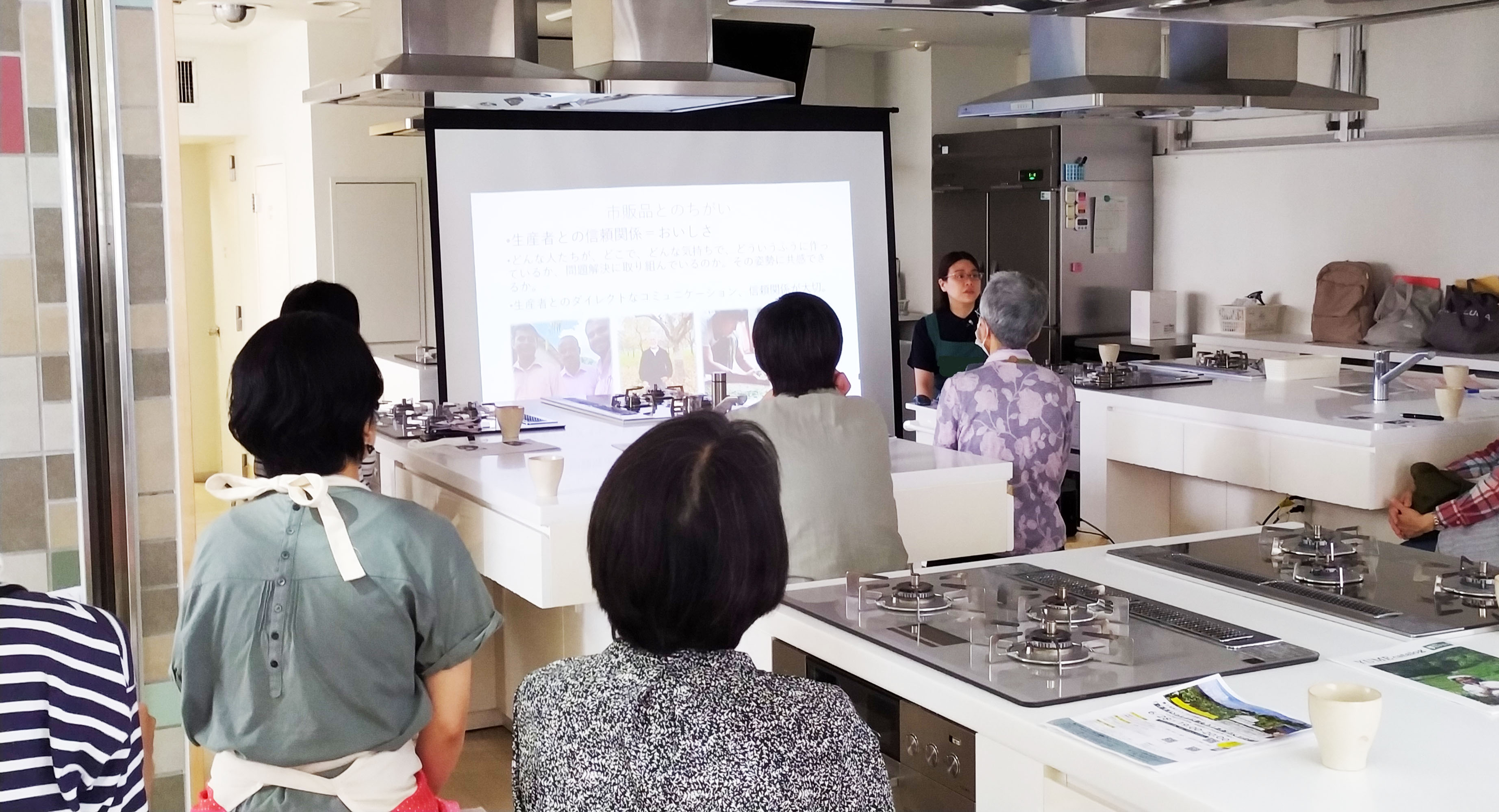
フェアトレード商品を使った料理イベントに登壇する山﨑さんの様子。
業務は幅広く、フェアトレードの魅力をさまざまな形で伝えている
――偶然の出会いだったんですね! 他の社員のみなさんが、どのような経緯で入社したのかも気になります。
山﨑さん:
私も気になって、何名かに聞いてみたんですよ。
ある社員は、前職でアジアのファッション工場の厳しい労働環境を目の当たりにして、JICA海外協力隊へ。
そこでボランティアの限界を感じ、「ビジネスとして課題を解決したい」と思って入社したそうです。
また、「チョコレートが美味しかったことがきっかけ」という、商品の魅力に惹かれて入社した社員もいました(笑)。
私もインターンシップの時に「第3世界ショップのチョコレート」 (前回(Vol.1)で紹介)がとても好きで食べ過ぎてしまったことがあります…。

たくさんの種類があるチョコレート。
「こだわって作られた商品は、自信をもっておすすめできます」
と山﨑さんは語る
――確かにチョコレート、魅力的ですよね。みなさん、最初から国際協力一筋というわけではなく、さまざまなきっかけがあるんですね。
山﨑さん:
そうなんです。
もちろん最初から「国際協力がしたい!」と入社する人もいますが、毎日の仕事とのギャップを感じる事もあるようです。
あとは「コミュニティトレード」は入社してから知ったという人は多いですね。
――たしかに、「コミュニティトレード」という言葉は、今回の取材で初めて聞きました。
山﨑さん:
もともと「フェアトレード」を事業の柱にしていましたが、創業当初から「貧困だけでなく、地域のさまざまな問題解決にも取り組もう」という姿勢だったんです。
国内の耕作放棄地でのお茶づくりや、持続可能な農業を続ける海外の生産者との取引など、フェアトレードの枠だけでは収まりきらない取り組みが増えてきたので、「コミュニティトレード」と呼ぶようになりました。

活動拠点は国内にも。
耕作放棄地になったお茶園を拠点にする「楠クリーン村」
では、自給自足の生活を実現している
品質管理も文化の違いも、一緒に乗り越えていく。現場で感じた「フェアトレードのかたち」とは?
――実際に、生産者の方々とやり取りする機会は多いのでしょうか?
山﨑さん:
私自身は生産者とのやり取りを担当していないので、経験は多くないですが、海外事業部の担当スタッフと一緒にスリランカやカンボジアなどへ出張し、製造工程を確認したり、営業用に販促のための取材をしたりしました。
文化の違いを実感することは多いですね。

現地で「カレーの壺シリーズ」のキャラクターモデル
ナンダさんにカレー作りを学ぶ山﨑さん
たとえば、「カレーの壺シリーズ」を生産しているスリランカは暑い国で、はだしにサンダル履きで過ごす人が多く、「工場に入る時に靴を履き替える」のを忘れやすい環境にあります。
そこで工場側は前室にベンチを設置して、腰かけないと工場内に入れない工夫していました。
そうすると自然に靴やサンダルを履き替えられるので、衛生面をしっかりクリアできるんですよ。
その国の文化や習慣に合わせた工夫が素晴らしいと思いますし、違いの面白さを感じます。

山﨑さんが主催している
オンラインイベント「第3世界ショップの小部屋」の様子
――実際に商品の製造面では、どんな苦労や面白さがありますか?
山﨑さん:
環境に配慮して添加物を使わない方針ならではの悩みもあります。
たとえば「カレーの壺シリーズ」 のレトルトカレーは増粘剤を入れていないので、中身がサラサラで個体差が出やすいんですね。
何度も撹拌しながら詰めても、ときどき「すごく薄いのが当たった」という声を聞くことがあります。本当にゼロにはできなくて、一緒に製造ラインを見直したり工程管理を徹底したり…今でも試行錯誤が続いています。
ドライフルーツも同様で、防腐剤を使わず「素材の味をそのまま届けたい」という想いがあるぶん、発酵しやすい。
そこで包材会社と協力し、袋のバリア性を高めるなど、話し合いを重ねてきました。

個包材にこだわった、ナッツやドライフルーツ
――まさに“一緒に乗り越えている”…ということですね。その中で、文化的な発想や価値観の違いなどで、意図せずトラブルが起こったりすることはありますか。
山﨑さん:
そうですね。
工芸品では「勝手に色やデザインを変えちゃった」という話もあります。
向こうでは「こっちの方が可愛いと思ったから変えたよ!」と好意でやってくれていることが、私たちにとっては大問題だったり(笑)。
でも、これは国や文化に限らず起こることかもしれません。
「乗り越えた」というより、毎回根気よく向き合って解決している感じですね。
――支援ではなく、ビジネスとして一緒にやっているからこそ、こうした切磋琢磨があるわけですね。
山﨑さん:
ええ。
スリランカの「カレーの壺シリーズ」のマリオさんは、工場に社員寮を用意して従業員や家族をしっかり支えています。
そうした安心感があるから、従業員たちもより良い品質管理にも取り組める。

スリランカの「カレーの壺シリーズ」工場の様子。
「仕事が楽しい」という、嬉しい声も聞こえてくる
インドの「ミラー刺繍」では、シスターが刺繍の仕上がりをチェックして、クオリティが低ければ容赦なくハサミを入れるそうですが、その厳しさが「商品として売れる品質」につながっているんです。
ひとつひとつの課題を地道に乗り越えていくことで、相互に成長し続ける――。
それがフェアトレード、あるいはコミュニティトレードの魅力だと思います。
フェアトレードが「ちょっと高い」「特別」と思われがち。その理由や理解を進めるために
――とはいえ、フェアトレード商品は「ちょっと高い」と思われることも多いですよね。
山﨑さん:
はい。でも、それは「生産者が無理なく続けられる環境づくり」のコストが含まれているからなんです。
たとえば農家さんに有機栽培を指導したり、家族で暮らせる社員寮を整備したり。長く続けるための環境整備には当然コストがかかります。
一方で、不当に安い価格には、誰かの「無理」が潜んでいるかもしれない。だから「少し高めでも、どこに手間とお金をかけているのか」を知ってほしいなと思います。

――近頃は物価の高騰もあって、安いものを手に取りがちですが、背景を知ると納得します。ただ、全員に丁寧に説明するのは難しそうですね。
山﨑さん:
ええ。だからこそ「まずは可愛い・美味しそう」という入口を大事にしているんです。
もともと中身には自信があるので、「美味しそう」「面白そう」と手に取ってもらえれば十分。
実はレシピ考案も私の業務の1つで、イベントを開催したりSNSで発信したりしていますが、それも「こんな使い方があるんだ!」と思ってもらうきっかけになれば嬉しいですね。

「カレーの壺シリーズ」のレシピ紹介写真
――最初の心理的なハードルを下げる努力は大切ですよね。今後はどんな形でフェアトレードを広めたいですか?
山﨑さん:
色んなお店で販売してもらったり、SNSでの情報発信、そして学生のインターンシップ受け入れなど、幅広くアプローチしていきたいです。
「フェアトレードを学びたい」と声をかけてくれた学生さんに「じゃあ一緒に何かやってみませんか」と呼びかけることもあります。
たとえばカンボジアから伝統舞踊のチームが来日したイベントでは、学生たちに運営を任せ、現地の文化や課題をリアルに感じてもらいました。
体験を通して、ファンになってくれる人が増えるといいなと思います。

「カレーの壺シリーズ」の生産者とともに参加した
「スリランカフェスティバル」の写真
「特別な買い物じゃなくて、日常の選択肢のひとつに」。読者へのメッセージ
――最後に、山﨑さんご自身がこの仕事を続ける理由や、やりがいは何でしょう?
山﨑さん:
生産者の情熱に触れたときの感動と、それを人に伝えられた時は、仕事をやっていて良かったなと思います。
先ほどお話ししたスリランカのスパイス工場で働く人たちが、皆さん楽しそうに活き活きしているのをみると、「私たちの仕事は本当に意味があるんだ」と実感できます。
インドのミラー刺繍生産者は、女性たちが刺繍で収入を得ることで家庭内の地位が上がり、さらに出産時に安心して過ごせるシェルターも整備されるようになりました。ビジネスを続ける中で、地域課題の解決にも繋がっていくんです。

「ミラー刺繍」をする生産者たち
――まさに支援ではなく、「一緒に作り上げるビジネス」なんですね。
山﨑さん:
はい。だからこそ、品質管理や納期の徹底など「うるさく言うなぁ」と思われるくらい、私たちも遠慮しません。
それから、お互いが違うことは前提としてあって、その相手の状況を考えながらお付き合いしています。
でも、その姿勢は生産者に対してだけではなく社内でも同じで、一人ひとりに合わせて個別対応してくれるんですよ。
子育て中でも働きやすいし、やりたいことがあればチャレンジさせてもらえる。そんな「人を大切にする」空気感が居心地の良さになり、私自身も長く続けられています。

同僚との打ち合わせの様子
それに「嘘をつかなくていい」ことも大きいですね。
本当におすすめしたい商品ばかりなので、自信を持って紹介できる。消費者の皆さんには気負わず、「可愛い」「美味しそう」という、直感で選んでもらえたら嬉しいです。
そこからフェアトレードに興味を持つ人がどんどん増えて、いつか「フェアトレード商品が当たり前に並んでいる世界」がくるといいなと思います。
編集者より
今回Vol.2では、プレス・オールターナティブの山﨑さんに、「現場でのエピソード」や「生産者との対話」を中心に伺いました。
フェアトレードが「支援」ではなく「共に成長するビジネス」であることが、よりはっきり伝わってきました。
少し値段が高めでも、それは現地の人が「無理なく暮らしていく」ためのコスト。そして、「可愛いから」「美味しそうだから」といったシンプルな理由で興味を持ってもらうことが、フェアトレードを日常に取り入れるための大きなきっかけになるのだと感じます。
お買い物で、フェアトレードの商品を見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。
そこから「こんな人が作っているんだ」「こんな工夫をしているんだ」と知っていくと、買い物がもっと楽しくなるだけではなく、きっとあなたならではの国際協力につながるのではないかと思います。
フェアトレード記事 Vol.1はこちら
☆フェアトレードの基本やフェアトレード商品を紹介した記事はこちら♪