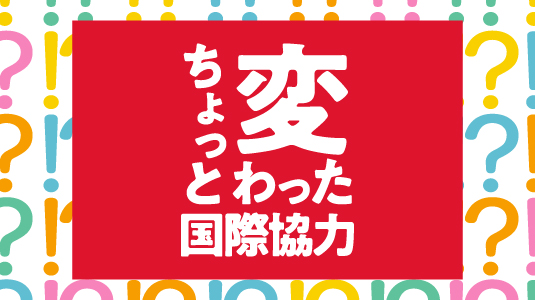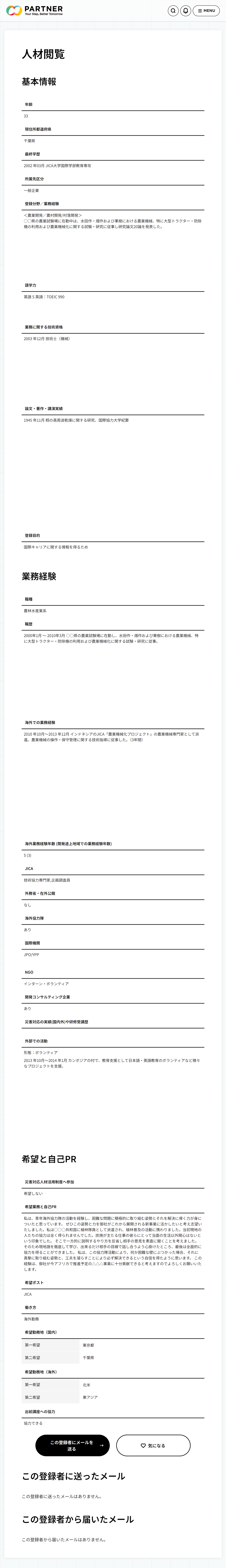「違和感」から始まったキャリア
──障害と社会の境界に向き合う、ヘラルボニー社員ふたりの選択

国際協力をはじめとする社会課題やSDGsに向き合う仕事をしたいと思う人は、多いのではないでしょうか。
今回は、障害をめぐる固定観念に向き合いながら、身近な「違い」を社会の可能性へと変えようとする、株式会社ヘラルボニー社員2人にインタビュー。
ヘラルボニーでは、主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、作品データのライセンス事業を展開しており、国内だけでなく途上国を含めた海外に関わる活動も行っています。
本記事では、そんな原体験と仕事観に迫り、「支援」ではなく「共創」という関わり方のヒントを探ります。
知的障害のある兄を持つ原体験から、「障害」に対する社会側のイメージ変容を志し、2023年3月に参画。企業や行政との共創を通じて、”違い”を魅力として伝えるプロジェクトを推進している。
自身の斜視をきっかけに「障害者」と言われた経験から、偏見が生まれる構造に関心を持つ。2021年12月にヘラルボニー社のインターンを経て、翌年新卒で入社。現在は人事労務として、多様な個性が尊重される組織づくりを担っている。
(こちらもオススメ!)2人の仕事観や日常、そして国際協力との接点とは?: “フラットである”という選択 ──ヘラルボニーの仕事から見えてきた、「ともにつくる」かたち
日々の業務の中でのやりがいとは?
――お2人が業務のなかでやりがいを感じる瞬間や、ミッションと重なる点を教えてください。
亀山さん:
ヘラルボニーの「異彩を、放て。」というミッションには、「障害」を「欠落」ではなく「違い」の一つとして捉え、その違いがあるからこそ生み出されるアートを世の中に発露することで、リスペクトに変えていきたいという思いが込められています。
私がやりがいを感じるのは、この事業を通じて、連携する方々の障害に対するイメージが変化する兆しを感じたときです。
最初は支援・貢献の文脈で作家や作品を見ていた方が、コミュニケーションを重ねるにつれて「純粋に作家・作品そのものが素晴らしいから、一緒にやりたい」と価値を感じてくださるようになったときは特に、自分の仕事がミッションと直接繋がっていると感じます。

ミッションである「異彩を、放て。」は、銀座の店舗にも大きく掲げられている
――山本さんは、社内業務が中心ですよね。やりがいを感じるのはどんなときですか?
山本さん:
インターンから新卒での入社後、ずっとバックオフィス業務を担当しています。
プロダクトが売れるたびに発生する作家報酬の計算業務が増えることで 、それを通じて「ミッションがビジネスとして回っている」と感じました。
また 人事・労務担当として、みんなが安心して働ける場を整えることが、外に「異彩」を届ける力になると思っていて。
会社の根幹を支えている実感があります。
「違和感」がキャリアの原点になった瞬間
――今の価値観や仕事の選択に影響を与えた、心に残っている出来事について伺いたいです。まずは山本さんからお願いします!
山本さん:
小学生の頃、障害のある友達とよく遊んでいて、その頃はただ純粋に「一緒に遊ぶのが楽しい」という関係でした。
でも、中学生になって「障害」という言葉を知ったときから、彼女を「助ける対象」として見るようになってしまって。
いつの間にか「面倒を見なきゃ」っていう義務感に変わっていたんだなと気づいたんです。
――その後、高校ではボランティア部に?
山本さん:
はい。
障害のある方の余暇活動をサポートする部に所属していて、障害のある人との関わりは多い方だと思っていました。
でもある日、友達とプールに行ったときに、私の斜視を見た小学生に「障害者がいる」と言われて。そのとき思わず「嫌だ」と感じたんです。
――自分のなかに偏見があると気づいたんですね。
山本さん:
はい。
ずっと近くにいたはずなのに、それでも「障害のある人=できない人」って、潜在的に偏見を持っていたことに気づきました。

それがきっかけで、「障がいのある人に対する偏見っていつ生まれるのか」「どうすれば減らせるのか」というテーマにすごく興味を持つようになったんです。
――ありがとうございます。亀山さんはいかがでしょうか?
亀山さん:
3歳上の兄がいて、彼には軽度の知的障害があります。兄のことは大好きでした。
小さい頃は一緒にお出かけをしたりゲームをしたり、たくさんの時間を共有してきました。

でも小学校の高学年頃から、友達に「なんかお兄ちゃん変だよね」と言われるように。それがすごく嫌でした。
そこから「人と違っちゃいけない」、「自分は「普通」でいなきゃ」と意識するようになりました。
それ以来、「普通」じゃない兄を避けるようになり、一緒に過ごす時間はどんどん減っていきましたね。
――そんな思いを抱えながら、どんなタイミングで気持ちに変化があったのでしょうか?
亀山さん:
気持ちに変化があったのは、社会人になってからです。
前職で忙しい日々に追われていたなか、久しぶりに実家に帰省した際、兄が子供の頃から変わらない笑顔で「おかえり!」と迎えてくれたんです。
何気ない一言だったんですが、なぜかその時の自分にはすごく響いて。
「自分は変わってしまったが、兄は変わらずずっとそばにいてくれたんだ」と感じ、これまで兄を避けていた自分を恥じました。
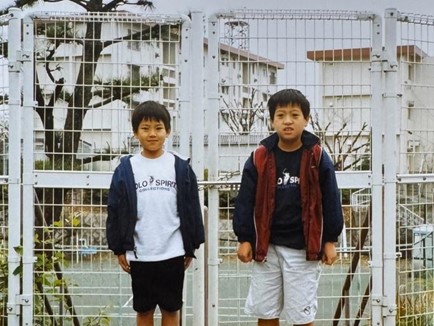
そして、「兄が笑顔で、幸せに過ごせる社会をつくりたい」「『違い』を『いいね』と受け入れられる世界を広げたい」と強く思うようになり、それが今のキャリアにつながっています。
自分の夢が、会社の未来に。「ヘラルボニー」を選んだ理由とは?
――お2人が感じてこられた違和感が今のお仕事につながっているように感じました。改めて、ヘラルボニーを選んだ理由を教えてください!
亀山さん:
前職は通信業界で、8年ほど働いていました。
仕事は楽しかったですが、いつも頭のどこかに兄の存在があって、「いつか兄に近い仕事がしたい」という思いを持っていました。
障害福祉に関する仕事も幅広く見ていたものの、どこかピンとこない。
選択肢を探すプロセスの中で、自分は「昔の自分のように、障害に偏見を持っている人の意識を変えたい」という思いが強いことに気づきました。

――ヘラルボニーとの出会いはどこだったのでしょうか?
亀山さん:
障害福祉に関する企業をネットで調べていたとき、偶然見つけて。
支援ではなく、ビジネスを通じて社会側の偏見にアプローチしている姿勢に共感して、迷わず応募しました。
――入社後、お兄さんへの気持ちに変化はありましたか?
亀山さん:
昔は「一緒にされたくない」と思っていたけど、今は「いつか一緒に働けたらいいな」と自然に思えるようになりました。
いま、ヘラルボニーでは岩手の ISAI PARKで運営しているカフェで施設外就労の方にキャストとして働いていただいているのですが、他にも新しい事業を構想していて。
将来もし兄と自分が同じ場所で働けたら…多分、感極まって泣いてしまうと思います(笑)

盛岡・カワトク百貨店に誕生した 実験場Cafe&Dining&Bar「無題」
山本さん:
亀山さんが泣きながら接客しているところ、ちょっと想像しちゃいました(笑)
亀山さん:
ありえますね(笑)
でも、兄が幸せに生きられる選択肢をつくることが、多くの障害のある方やそのご家族の可能性を広げていくことにもつながると信じているので、チャレンジしていきたいです。
――自分の夢が、会社の未来にもつながっているのですね。山本さんはいかがでしょう?
山本さん:
私はずっと、「障害」と「健常」という二分化の解消を実現したいと思ってきました。
大学では、学生時代の経験をもとに潜在的な偏見はいつ、どうやって生まれるのか」をテーマに研究していて、その延長でヘラルボニーに出会ったんです。

特に心に残っているのが、2021年の意見広告
「この国のいちばんの障害は「障害者」という言葉だ」
というもので、私も思っていたことでした。
「障害」は、外にあるものとして捉えやすいのに、「障害者」となると、それが個人に内在化されてしまう感覚がある。
だからこそ、ヘラルボニーの発信がもっと広がれば、私のように偏見を内面化してしまう子どもが減るんじゃないかと思ったんです
「障害って、違いでしかなくて、むしろ面白いよね」って、心から言える社会にしたい。そんな未来をつくりたいから、私は今ここにいます。
「国際協力」との接点
――ここまでお互いの話を聞いて、改めてどう感じましたか?

山本さん:
話す機会は多かったですが、亀山さんのお兄さんの名前は今日初めて知りました(笑)
亀山さん:
確かに、初めて言ったかも!
JICAさんとの共創で国内外の障害のある作家同士の交流を広げることを目的の一つにタイのアジア太平洋障害者センターに行ったのですが、そのときに、すごく打ち解けましたよね。

タイに視察に行ったときの様子
――お2人は「国際協力」という言葉をどう捉えていますか?山本さんはJICAインターンも経験されていますよね。
山本さん:
私にとっては身近な言葉です。
中1の頃、マララ・ユスフザイさんのニュースを見て、ただ「学校に行きたい」と言っただけで命の危険がある現実に衝撃を受けました。
そこから、開発途上国にずっと興味があり、高校生でネパールへ留学しました。
ストリートチルドレンや障害のある方にも出会い、自分に何ができるかを考える中で、お金を渡す以外の継続的な関わり方ができないかとずっと考えています。
ヘラルボニーとJICAさんとの共創にはその可能性を感じています。
――亀山さんは、これまで国際協力を意識する機会があまりなかったのでは?
亀山さん:
そうですね、正直、「国際協力をするぞ」と強く意識したことはないです。
でも、障害のある人とそのご家族の環境や課題を見ていくなかで、「これはきっと日本だけの話じゃない」と感じるようになりました。
実際、海外の作家さんと契約する機会もあって、「海外の障害福祉・アートの実態はどうなっているんだろう」と興味を持ったタイミングで、ご縁がありタイへの視察に参加しました。
気づけば、自分たちの活動が地続きで世界に広がっている…。
そんな実感があります。

――普段はあまり意識していなくても、結果的に活動が国際協力へとつながっているのですね。
編集後記:編集者より
兄や友人との関わりを通じて感じた違和感を、キャリアの軸としてきた2人の話から見えてきたのは、海外に行かなくても、身近な「違い」と向き合う選択が社会を動かす力になるということ。
特別な原体験がなくても一歩は踏み出せるし、「当たり前」を問い直す視点が変化を生むのだと感じました。
次回は、そんな2人のプライベートや、より深い想いに迫ります。
ヘラルボニー記事 Vol.2はこちら
☆ふたりの仕事観や日常、そして国際協力との接点に迫った記事はこちら♪