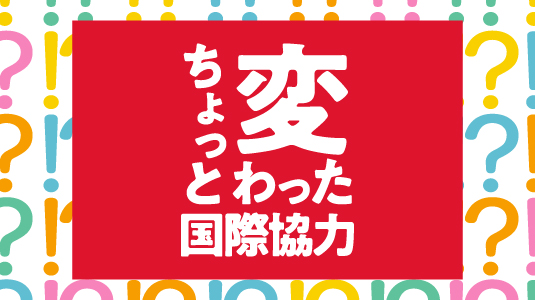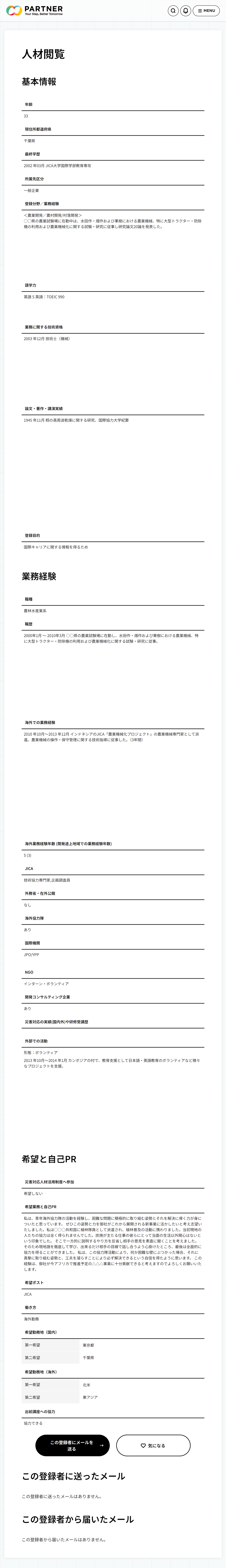“フラットである”という選択
──ヘラルボニーの仕事から見えてきた、「ともにつくる」かたち

Vol.1
では、株式会社ヘラルボニーで働く亀山さんと山本さんに今のお仕事に行きついたきっかけや原動力についてお伺いしました。
Vol.2では、そんなふたりの仕事観や日常、そして国際協力との接点までを紐解いていきます。
知的障害のある兄を持つ原体験から、「障害」に対する社会側のイメージ変容を志し、2023年3月に参画。企業や行政との共創を通じて、”違い”を魅力として伝えるプロジェクトを推進している。
自身の斜視をきっかけに「障害者」と言われた経験から、偏見が生まれる構造に関心を持つ。2021年12月にヘラルボニー社のインターンを経て、翌年新卒で入社。現在は人事労務として、多様な個性が尊重される組織づくりを担っている。
(こちらもオススメ!)ヘラルボニーで働くきっかけとなった現体験や仕事観に迫った記事: 「違和感」から始まったキャリア ──障害と社会の境界に向き合う、ヘラルボニー社員ふたりの選択
“ちがい=素敵なこと”を、自然に受け取れるのがアートの魅力
――ヘラルボニーでは、たくさんのアートや、それを落とし込んだ商品を展開していますよね。「障害者アート」のような言葉に対する社会のイメージに、違和感を覚えることはありますか?
亀山さん:
そういった括り方をすることで、隔たりを感じやすくなってしまう気がします。
障害がある・ないを取っ払って、フラットに作品が見られている状態がいいなと思いますね。
なんて偉そうなことを言っていますが、私、実はもともとアートに興味があったわけではなくて。
ヘラルボニーに入社を決めたのは、会社の理念や目指す世界観に共感したから。扱うものが何かは、あまり重要ではなかったんです。

山本さん:
私も同じです。でも、アートに惹かれて入社する人もいるので、初めの関わり方は社内のメンバーでも人それぞれですね。
亀山さん:
確かに。
私も「アートに興味がなかった」と言いつつ、今では美術館に行くようにもなりました。
それは、入社してからアートの魅力を感じるようになったからだと思っています。
作家1人1人の個性や生き様は本当に多様だし、作品に対する解釈は見る人によって違ってくる。
「ちがいって、面白い」ということをすっと感じられる点で、アートはすごく可能性があるなと感じるようになりました。

銀座にある店舗には、定期的に作家やテーマごとの
展示を行うギャラリーが併設されている
――表現に正解がないからこそ、捉え方が自由で、コミュニケーションも生まれますよね。
「支援する・される」ではなく、“フラット”であるという働き方
――障害のある方に関わる仕事は、「支援する・される」という構造で捉えられることが多いですよね。そういった見方に対して、違和感を抱くことはありますか?
山本さん:
学生時代、国際協力に関心を持ち始めたころは、“助けてあげなきゃ”という気持ちで関わっていました。
国際協力の現場も同じだと思っていて。
高校生の時に初めて訪れたネパールは、毎日突然停電するなど日本では経験しなかったことをたくさん経験しました。
ネパールに行くまでは、そのような状況があることを聞いていたので「かわいそうだな」と思っていたんです。

ネパール留学中の山本さんの様子
でも実際にネパールに行ってからは「かわいそうとは違うかも」と思い、だんだんと考え方が変わっていきました。
今は、「支援したい」「助けてあげたい」というより、「私がネパールが好きだから、大好きなネパールの人と一緒になにかをできれば嬉しい」という気持ちの方が強いですね。
――亀山さんは、どのようなときに違和感を感じますか。
亀山さん:
「(障害のある人が描いたアートを)使ってあげることは、良いことだ」という考え方をされる人は、一定いらっしゃると思います。
もちろん、その考え方自体が悪いというわけではないのですが、私は違和感を感じます。
作家のストーリーをお伝えしたり、実際にご本人にお会いしていただくていく中で、「この素敵な作品を描いている〇〇さん」と具体的な一個人にスポットが当たり、リスペクトが生まれる瞬間があります。

JICAのみなさんと一緒に福祉施設に訪問した際のようす
そのとき、「障害」という言葉が持つネガティブなイメージが、色鮮やかに塗り替えられていくような感覚になるんです。
私にとって、すごく印象的な瞬間です。
個人的な経験から始まる原点
――誰かと対等な関係で取り組む姿勢や、つくる過程を大事にしているという点が、お二人の共通点のように感じます。仕事のうえで大切にしているスタンスはありますか?
亀山さん:
「障害のある人を支援する」という文脈になりがちですが、私たちはむしろその逆で、作家に依存していると自覚しています。
たとえば、ネクタイの製造においては、ただのプリントではなく「織り」でアートの質感や奥行きを再現するなど、細部にまでこだわっています。
作家・作品へのリスペクトを持っているからです。

工藤みどりさんの作品を落とし込んだネクタイ
作品の風合いが繊細に表現されている
作家がいなかったら私たちのビジネスは成り立たない。
だからこそ、「一緒につくっている」という対等な関係を大事にしています。
山本さん:
本当にそうですね。
社内では「これは本当に『障害の概念を変えられている』と言えるのか?」といった問いが自然に出てくる環境で、みんながその感覚を大事にしていると感じます。
また、亀山さんの「アートが固定観念をほどく力を持つ」という話を聞いて、自分の『障害と健常の二分化の解消』というミッションと重なるなと改めて感じました。

私の中には、「国際協力」と「障害」という2つの軸があって。
将来的には、大好きなネパールの障害のある人たちとなにかを一緒にできたら嬉しいです。
――プライベートの過ごし方についても、少し教えてください。
山本さん:
出身は関西、大学や大学院は関東、今は岩手で働いているので、いろいろな場所に友人がいます。

休日に社内のメンバーとわんこそば大会をした様子
東京出張で大学や大学院の友人と会ったり、留学やインターンで出会った仲間とも交流したり…。
高校の友人とはつい最近カラオケに行きました(笑)
亀山さん:
私も友人とご飯に行くことが多いですね。
あと、家族とは今でも旅行に行きますが、たまに“仕事が忙しそう”と仲間外れにされることもあります…(笑)
“国際協力”はもっとラフでいい。読者へのメッセージ
――「国際協力」と聞くと、“意識が高い人の話”に思えてしまう方もいるかもしれません。そうした方々に、どのように伝えたいですか?
亀山さん:
強い使命感があるかどうかより、純粋に「面白い」と思えるかどうか。
国際協力という大きく見えるテーマにおいても、まずは自分の感情に向き合うことが大切なんじゃないかって思います。
実際、ヘラルボニーには「社会課題を解決したい」「障害福祉に関わりたい」というよりも「アートが好きで入った」メンバーもいますから。

山本さん:
たしかに、「国際協力」からイメージするキャリアって、すごく高い壁があるように見えますよね。
私も「国際協力といえば国連。国連を目指すには最低でも修士号が必要」と思っていたので、高校生の時に大学院までは絶対に進学しようと決めていましたが、今振り返ると「正解」をなぞっていた感覚です。
きっとそれだけじゃない選択肢があるんだなと今は思います。
採用活動をしていても「原体験がないから…」と教えてくださる方もいますが、障害や国際協力に関わってきた経験は必須ではないと、私は思います。
言語の壁や不安があっても、やってみたいという気持ちや自分の中で大切にしている軸などがマッチしているのであれば、門戸は開かれていると思います。
亀山さん:
ヘラルボニーの仕事も「社会貢献」という側面が強く見えるかもしれませんが、重要なことは「いいことをしている」ことではなく、「いいものをつくる」という営みの先に、自然と人の感情が動かされること。
そんな考え方をこれからも大切にしていきたいと思っています。

編集者より
ヘラルボニーのお二人とお話しして印象的だったのは、「社会を良くしたい」という想いが、決して特別なものではないということでした。
大切な誰かのことを思う気持ちや、日常の中で感じた小さな違和感。
それらに向き合いながら、「誰かと何かをつくる」ことを選び取っていく。
その積み重ねが、結果として社会を動かしていく力になるのだと思います。
海外に行かなくても、特別なキャリアを歩まなくても、協力は始められる。そんな実感を手渡してくれるような時間でした。
ヘラルボニー記事 Vol.1はこちら
☆ヘラルボニーで働くきっかけとなった現体験や仕事観に迫りを紹介した記事はこちら♪