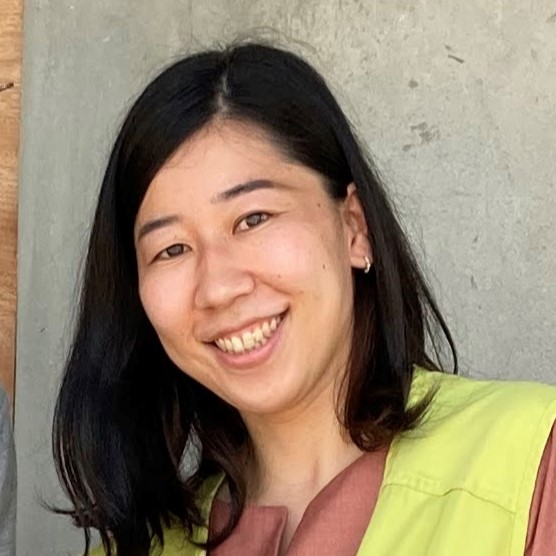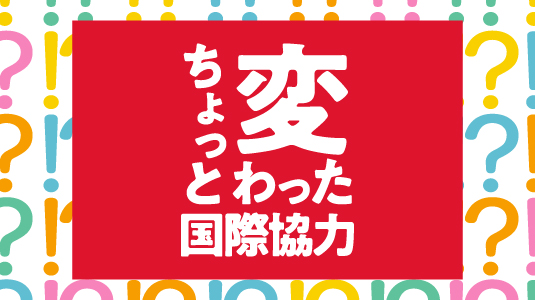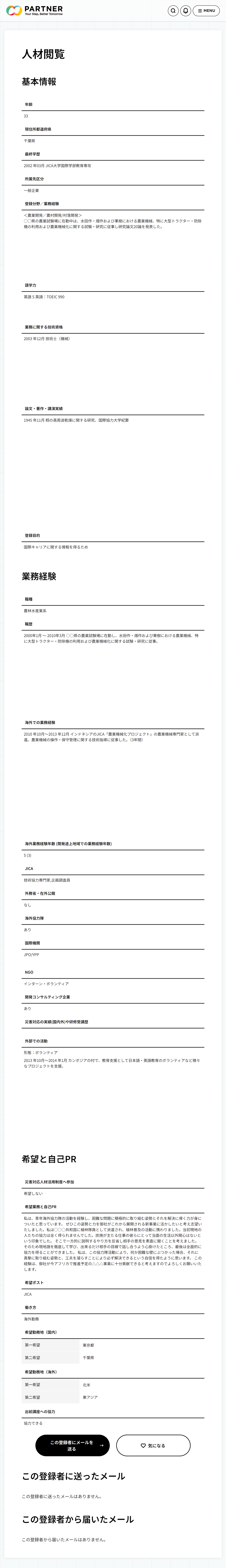アフリカで奮闘する若手駐在員に聞いた!
なぜモザンビークに?国際協力現場のリアルとは?

国際協力業界では、実際に海外に駐在しながら仕事に携わることも少なくありません。しかし、結婚、出産、育児などのライフイベントとキャリアをどのように両立していくのか、疑問や不安のある人も多いはず。
そこで今回は、モザンビーク共和国で活躍する、2人の若手駐在員にインタビュー!
現地での仕事や生活のリアル、今後をどう考えているか?を伺いました。本記事(Vol.1)では、2人のこれまでの経歴やモザンビークでの活動内容、仕事への想いを紹介します。
(こちらもオススメ!)モザンビークでの日々の暮らしや、ライフプラン、そして将来の展望を紹介した記事: 『モザンビークでの生活、これからのこと ──若手駐在員が語る魅力、苦労、そしてライフプランを聞いてみた!』
モザンビークで働く2人。現在の仕事や、国際協力の道へ進んだきっかけとは?
――お忙しいなか、取材を受けていただきありがとうございます!お2人は知り合いだと伺っているのですが、知り合われたきっかけは何だったのでしょうか?
塩崎さん:
平良さんとは、モザンビークで共通の友人を通じて知り合いました。
モザンビークには日本人が130人ほどしかいなくて、コミュニティみたいなものが存在するんです。同年代の日本人と交流できる機会はすごく貴重ですね。
大使館の同僚が、平良さんと意見交換をしているのが隣の会議室から聞こえてくるとき、いつか関われたらいいなと思ったりします(笑)。

現地の日本人コミュニティで食事をしたときの写真。
月1程度で集まっている
平良さん:
モザンビークの日本人コミュニティは小さいので、みんな顔見知りになれると思います。
塩崎さんは国連関係の資金を取り扱っているので、仕事での直接的な関わりはありません。将来的には、グッドネーバーズ・ジャパンとしても日本の政府開発援助(以下、ODA。政府資金で行われる、開発途上国などに対する援助や協力のこと)を活用したより大きな事業に取り組んでいきたいと考えています。
――仕事での直接的な関わりはないのですね。では、現在のお2人の仕事内容について教えてください。
塩崎さん:
私は、モザンビークの日本大使館で経済協力調整員をしています。
日本のODAを効率的に運用するために、他国のODAやモザンビーク政府のニーズを調査し、日本が行う政策に提言するのが主な仕事です。
具体的には、国連機関と連携した事業の立案、予算管理、事業進捗管理などを行っています。
例えばモザンビーク北部では、2017年から続くテロの影響で、多くの国内避難民が発生しています。そこで、UNDPと連携し、13億円規模のインフラ復興事業を立ち上げました。
道路や橋、学校など、多くの人が使う施設の再建を支援することで、避難民の生活をサポートしています。

塩崎さん
平良さん:
私はグッドネーバーズ・ジャパンというNGOに所属しています。
モザンビークで実施している事業の管理が主な仕事で、具体的には、現地スタッフの採用・業務管理、予算管理、現地政府との調整、日本大使館への進捗報告などを行っています。
赴任当初は、農村部で保健医療サービスの普及を目的とした事業を担当。ヘルスセンターの建設やコミュニティヘルスワーカーの育成などを通して、地域住民の保健医療サービスへのアクセス改善に努めました。

平良さん
――先日、モザンビークでサイクロンが発生したというニュースを見ました。その対応などもされているのでしょうか?
塩崎さん:
はい、2024年末に北部でサイクロンが発生して、大雨による浸水や停電などの被害があったので、支援ニーズに関する情報収集や、可能な支援の実施といった対応もしています。
どこにどんなニーズがあるかということを、迅速かつ慎重に判断するのは難しいですが、住民の生活に直結することになるので、責任を感じる仕事です。
なぜモザンビークで働くことに?それぞれの経歴を深掘り
――なぜ日本から遠く離れたモザンビークで働くことになったのでしょうか?きっかけや具体的な道のりを教えてください。
塩崎さん:
大学時代にポルトガル語を専攻していて、メジャーな留学先はブラジルかポルトガルでした。
でも、その時に何を思ったのか「ちょっと違うことをやりたいな」と思って。自分にとって最も遠い場所、という感覚のアフリカへ行きたいと思い調べたところ、ポルトガル語圏が5か国存在し、その中のメジャーどころの1つがモザンビークでした。

学生時代にモザンビーク滞在中の塩崎さん
現地の大学に1年間研究生として受け入れてもらい過ごすうちに、人や土地がすごく好きになったんです。また、国が社会主義から資本主義に変わって、これからどうなるのかという部分にも興味を持ちました。
大学卒業後、オランダのライデン大学でアフリカ研究の修士を取得。「いつかモザンビークに戻りたいな」と思っていたところに、このポジションを見つけ、応募。ご縁があって現在に至ります。
――なるほど。ファーストキャリアがモザンビークなのですね!平良さんはいかがですか?
平良さん:
私は大学卒業後、日本の企業で営業職として4年間働いていました。
もともと、NGOで働きたいと思っていましたが、実務経験を求められる場合が多かったので…。日本企業で働く経験は海外で活かせるというアドバイスもいただいたことから、最初のキャリアを始めました。
営業職を選んだのは、学生時代にNGOでインターンをした際に、資金繰りが苦しいという現場を見て、「人はどういう理由でお金を使うのか」を知りたかったからです。
その後は、タンザニアでJICA海外協力隊として活動していたのですが、コロナ禍で撤退。その後転職し、現在のグッドネーバーズ・ジャパンに入職しました。
そのタイミングで、団体内で「モザンビークで事業が始まりそうだし、タンザニアで活動した経験があるので合うのでは」とオファーをもらったんです。私も、またアフリカで働きたいという気持ちがあったため、そのオファーを受け、今に至るという流れです。

JICA海外協力隊時代の写真
仕事内容を紹介!現地での活動内容とは?
――モザンビークでの業務内容について、もう少し詳しく教えてください。
塩崎さん:
国際機関を通じたODA事業を担当しています。具体的には、ユニセフやWFPなど、様々な国際機関と協力して、人道支援や開発協力を行っています。
例えば、ユニセフと連携した保健事業では、妊産婦や子どもの健康改善のための支援。
WFPと連携した食料支援では、日本からモザンビークにお米やサバ等の魚の缶詰を輸送し、現地の人々に配布しています。
サバ缶って、「ザ・日本食」というイメージだと思うのですが、意外と現地の人にも人気なんです。

国際機関(FAO、IOM、UNHCR) を通じた
人道支援事業の開始式での集合写真
――サバ缶。確かに驚きました(笑)。平良さんはいかがですか?
平良さん:
私の場合は、これまでに保健衛生と水衛生の事業を担当してきました。
保健衛生の事業では、ヘルスセンターの建設やコミュニティヘルスワーカーの育成などを行っています。コミュニティヘルスワーカーとは、地域住民の健康状態をチェックしたり、健康に関する知識を普及したりする役割のことですね。
水衛生の事業では、安全な水へのアクセス改善に取り組んでいます。具体的には、給水システムの建設や修繕、学校トイレの建設、衛生教育などを行っています。
――給水システムやトイレの建設は、生活に直結する重要な支援ですね。もう少し詳しく教えていただけますか?
平良さん:
はい。モザンビークの農村部では、安全な水へのアクセスが限られている地域が多く、水不足や野外排泄などの不適切な衛生行動を原因とする健康被害が深刻です。
給水システムの建設を行う際には、まず地下水の水質調査や水量測定を行い、安全で持続的な水源を確保できる場所を選定します。
そして、地域住民と協力して給水システムを建設し、維持管理の方法を指導していくんです。
トイレの設置では、衛生的なトイレの必要性を理解してもらうための啓発活動を行いながら、地域住民が主体的にトイレの建設や維持管理に取り組めるよう支援しています。

平良さんが現地の学校で、衛生啓発をしている様子
――なるほど。設備を整えるだけでなく、地域住民の意識改革も必要なのですね。
モザンビークで働くということ――課題、やりがい、そして成長
――次に、課題だと感じることや、その乗り越え方を教えてください。
塩崎さん:
モザンビークでは、政治状況が不安定な時期があり、事業の進行が遅れてしまうこともあります。
また、インフラも整備されていないので、物資の調達や輸送が困難で、計画通りに進まないことも多いです。でも、臨機応変な対応力が身につき、新たな発見や学びにつながっています。
平良さん:
私はモザンビークに来て、コミュニケーションの難しさを改めて実感しています。文化や習慣の違いから、日本では当然のように理解してもらえると思っていたことが、伝わらないケースもあるんです。
簡単な指示では伝わらないことがあるので、業務を依頼する際は、背景や目的、具体的な内容を細かく説明します。また、進捗報告も待つのではなく、自分から積極的に確認するようにしています。

チームメンバーと平良さんの集合写真
――これまでの仕事のなかで、特に印象に残っているエピソードはありますか?
平良さん:
2つあって、1つ目はヘルスセンターの開所式での出来事。
地域の人々や建設作業員、看護師など、事業に関わる全員が、ダンスを踊り始め、ヘルスセンターの完成を一緒に喜んでいる姿を今でも鮮明に覚えています。
もう1つは給水施設を作ったとき。引き渡し式で地域の方々がものすごく喜んでくれて、蛇口から出る水をゴクゴク飲んで「ありがとう、ありがとう」と何度も言ってくれました。
そういう、喜びや感謝の気持ちをストレートに表現されることが嬉しいですし、やりがいに繋がります。

給水施設の修繕前(写真左)と後(写真右)
――ダンスというのは、陽気なアフリカの国らしくて素敵ですね。塩崎さんはいかがですか?
塩崎さん:
私も2つ、印象的なエピソードがあります。
1つはフィールドビジットで支援先に行ったときのことです。僕らの業務は大使館内でのデスクワークが多いので、現地には年に3、4回行けるくらいなのですが、そこで実際にODAの物資が届いているのを確認したんです。
州都から車で2時間ほどの保健センターで、公共交通機関もない、医療スタッフの数も足りていない、利用できる救急車にも限りがあるといった場所でした。
日本からの医療物資が届き、大事に使われている姿を見て、「届けるべき場所にしっかり届いているんだな」と実感できて、嬉しかったのと同時に安心したことを覚えています。

日本の支援物資が届いている様子
もう1つは、国内避難民(IDP)の方々と直接お話ししたとき。
戦禍を逃れてきた人々の生々しい体験談を伺って、人々が単なる数字ではなく、一人ひとりが大切な存在であることを改めて実感し、日本の支援の意義を深く考えさせられました。
――確かに、自分の目で確かめられることは、現地で働くなかで大きな魅力ですね。改めて、モザンビークで働いていてよかったなと思うことは何でしょうか?
塩崎さん:
私は、さまざまな人と出会い、交流できることが嬉しいです。モザンビークの人々だけでなく、世界中から集まった人たちと交流することで、視野が広がりました。
平良さん:
そうですね…やはり、地域の人々に貢献できていることを、自分の身で感じられることですね。
編集者より
今回は、モザンビークで国際協力の仕事に携わる、平良さんと塩崎さんに、お仕事内容やモザンビークで働くことになったきっかけ、やりがいなどを伺いました。
日本とは異なる環境や文化の中で業務を進めていくことは困難も多いと想像できますが、現地の皆さんの喜びが直接感じられるとやりがいも大きそうです。
同じモザンビークで働くお2人ですが、日本大使館・NGOと立場が異なると、活動内容や支援方法に違いがあることも興味深いですね。
次回は、2人の現地での生活や、今後のライフプランについて深堀りします。結婚や出産、キャリアとの両立など、気になる話題が満載です。お楽しみに!
モザンビークで働く若手駐在員へのインタビューVol.2はこちら
☆日々の暮らしや、ライフプラン、そして将来の展望について深掘りした記事はこちら♪