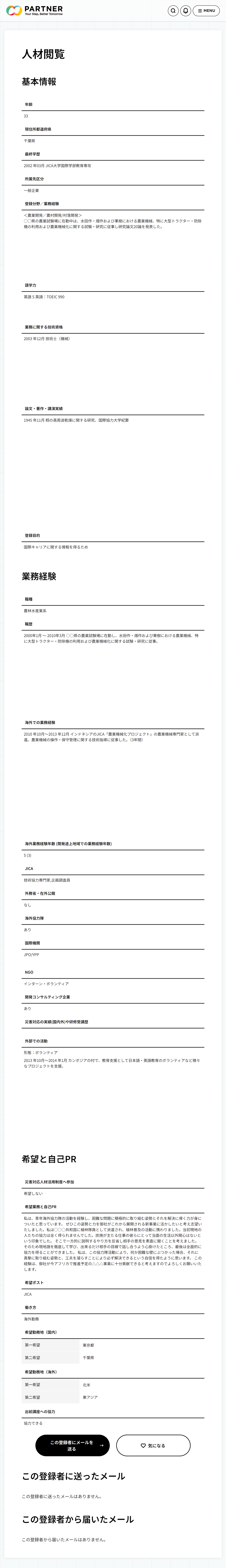登録団体詳細
一般社団法人 土佐れいほく観光協議会
団体情報
- 団体名
- 一般社団法人 土佐れいほく観光協議会
- 団体種別
- 国際協力実施団体(法人格有)
- 所在地
- 高知県
- 設立年月
- 2020/ 12
- 設立目的・事業内容
- 一般社団法人土佐れいほく観光協議会は、四国の中央部・高知県嶺北地域(本山町・大豊町・土佐町・大川村)を対象に、観光を通じた地域づくりを推進することを目的として、2020年に設立された地域連携DMO(観光庁登録法人)です。人口減少・高齢化・担い手不足といった中山間地域特有の課題に対し、観光を「地域の資源と人をつなぐ公共インフラ」と捉え、持続可能な地域経済の構築と地域社会の活性化を両立させることを目指しています。 当協議会では、四町村・高知県・民間事業者・住民組織が一体となり、自然資源(川・山・棚田)や地域食材(土佐あかうし・棚田米・地酒)、暮らし文化(農村体験・民泊等)を活かした観光コンテンツを統合的に開発・発信。「教育民泊」「ガストロノミー」「清流アクティビティ」「SDGs実践」など、体験と地域課題解決を融合させた着地型観光を展開しています。 さらに、国際協力機構(JICA)四国センター、高知大学次世代地域創造センターとの3者連携協定を結ぶ本山町と協働し、国際協力・地域開発・開発教育のフィールドとしての活用も進めており、国際開発学会主催の「地域x国際エクスカーション企画」実施などを通じて、観光と国際協力の交差点に立つ地域モデルを構築中です。
- 活動分野
- 教育、市民参加、一般事務・経理、日本国内の社会課題への対応・多文化共生、多岐にわたる分野
- 活動国
- 日本
- 活動実績(国内)
- 【主な活動分野】 ・地域観光の統括マネジメント(マーケティング、商品造成、販路開拓) ・教育旅行・教育民泊の受入(年間5,000人以上) ・地域内経済循環を生む滞在型観光の推進 ・インバウンド対応の体制整備 ・国際協力人材・教育機関との連携(JICA OJT、国際開発学会研修受入等) ・多文化共生・異文化理解の促進(外国人学生受入等) 【具体的実績と特色】 地域全体が観光の担い手となる仕組みを構築し、地元農林業者・宿泊・交通・行政・商工団体と連携した着地型商品(ラフティング/カヌー/SUP等の清流プログラム・日本棚田100選に選出された棚田を活用した観光商品・農家民宿・古民家の一棟貸など)を展開。観光庁のサステナブルツーリズム事業、インバウンド商品造成事業などにも継続参画し、高付加価値な観光体験を造成しています。 とりわけ教育旅行分野では、全国からの修学旅行受入に加え、台湾・香港・オーストラリア・ドイツなど海外からも毎年300人前後の外国人学生を受け入れ、農家家庭に宿泊する異文化体験を提供。これにより、地域住民の受入力や国際理解が高まり、多文化共生の基盤形成にもつながっています。 【今後の計画・展望】 現在は、地域に点在する農家民宿や一棟貸しの空き家などを束ねた「れいほくホテル構想」を推進中。外国人旅行者の長期滞在にも対応できる宿泊ネットワークの整備を進めています。各施設には地域住民が管理人として関与し、ガストロノミーツアーや清流体験などの体験プログラムと一体化することで、単なる宿泊以上の“暮らしに触れる滞在”を提供します。 今後は、観光分野の人材育成(ローカルガイド、ホスピタリティ人材)や、デジタル技術(DX)を活用した予約・管理体制の整備も計画。地域と海外、地域と都市、地域と若者をつなぐ「フィールド拠点」として、「観光×地域活性×国際協力」のクロスセクター型地域モデルを構築していきます。 【土佐れいほく観光協議会で働く魅力】 少人数体制ながら、自ら企画・運営・発信・連携まで一気通貫で取り組める環境です。JICAとの協働や大学連携、海外向け商品開発、教育旅行の現場運営まで、分野を超えた実践経験を積むことができます。 「観光×地域活性×国際協力」に興味がある方、地域に深く入りながらグローバルな価値創造を志す方にとっては、非常にチャレンジングでやりがいのある現場です。
- 活動実績(海外)
- SDGsへの取り組み