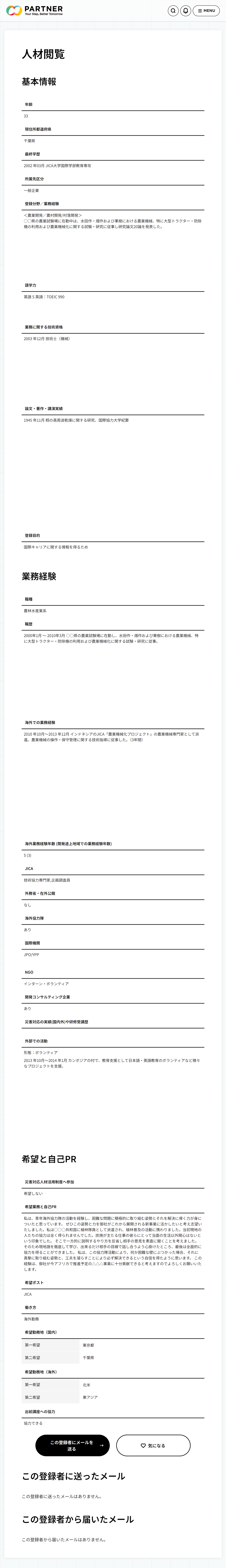プログラム/内容
- ジャンル
- セミナーシンポジウム
- 開催日時
- 2026/02/28 13:00 ~ 2026/02/28 16:30
- 開催地
- 神奈川県 日本 三浦郡葉山町上山口1560-39 湘南国際村センター地下1階国際会議場
- 開催形式
- オンライン・オフライン併用
- 内容
2016年度に公益財団法⼈かながわ国際交流財団の呼びかけで始まった、湘南・三浦半島地域の公⽴美術館が連携しながら、定住外国⼈や障がいのある⽅々を対象としたインクルーシブな教育普及事業の企画・実施を⾏う「マルパ(MULPA)※」プロジェクトは、地域の多様な背景を持つ⼈々とのつながりを深めるため、研修会やワークショップなどを展開してきました。2025年度末を持ってプロジェクトを終了するにあたり、どのような社会的意義が⾒い出せたのか、プロジェクトに関わってきた皆様とともに考えます。
※マルパ(MULPA)とは?
MULPAとはMuseum UnLearning Program for Allの頭文字を取った略称で、日本語では「みんなで“まなびほぐす”美術館―社会を包む教育普及事業―」としています。「unlearn アンラーン」とは、英語ではunlearn、日本語で「まなびほぐす」という意味です。ステレオタイプ化した美術館イメージを問い直す、という意味が込められています。
https://www.kifjp.org/mulpa/about
●⽇ 時:2026年2月28日(土)13:00~16:30(視聴入室12:30)
●開催方法:ハイブリッド(会場(対面)/ZOOM(オンライン))
●会 場(対面):湘南国際村センター地下1階国際会議場(神奈川県三浦郡)
●参加費:無料
●定 員:会場60名/オンライン100名
●内 容(プログラム):
【第1部】実績紹介~これまでのマルパ・プロジェクトの活動について~
・藤川 悠(茅ヶ崎市美術館学芸員)
・鈴木(中野)敬子(東京都写真美術館 事業企画課普及係社会包摂プログラム担当)
・小林 絵美子(藤沢市アートスペース学芸員)
・ホセイン・ゴルバ(アーティスト)※(通訳:段田尚子(イタリア語↔日本語))
・高山 明(演出家・アーティスト/演劇ユニットPort B(ポルト・ビー)主宰/東京藝術大学大学院映像研究科教授)
・渋谷 実希(一橋大学大学院・東京大学・津田塾大学 非常勤講師)【第2部】講演(対談)「マルパ・プロジェクトを“まなびほぐす”」
・ロジャー・パルバース(作家/映画監督)×水沢 勉(マルパ実行委員長/美術史家・美術評論家)
【第3部】コメントセッション
●申込締切:2026年2月25日(水)
●主催:マルパ実⾏委員会/公益財団法⼈かながわ国際交流財団
- 職務分野
- 教育、日本国内の社会課題への対応・多文化共生、多岐にわたる分野
- 会場名
- 湘南国際村センター地下1階国際会議場
参加資格
- 参加費用
- 無料
募集内容
- 学生歓迎
- 中高生歓迎;大学生・大学院生歓迎
- 募集人数
- 会場60名/オンライン100名
- 募集期間
- 2025/10/17 16:00 ~ 2026/02/25 23:59
申し込み方法
- 掲載内容の確認等は、ご利用者様、掲載団体様の両者間の責任で行ってください。掲載内容及びセミナー・研修プログラムは、独立行政法人国際協力機構(JICA)の見解を示すものではありません。詳しくは規約をご確認ください。
- 未成年が有償セミナーへ申し込むには保護者の同意が必要です。
- ウェブ応募時の個人登録者の個人情報の扱いは案件を主管する登録団体の定めによることとします。尚、Web応募を実施することにより、団体に対するプロフィール公開項目の提示に同意したものとみなします。
- 参加申し込み方法
- 開催団体のお知らせページ
- https://www.kifjp.org/mulpa/info/702
【ハイブリッド開催】マルパフォーラム2025 in Hayama「ほぐし ひらき つながる これからに」
公益財団法人かながわ国際交流財団
このイベントに似たイベントを探す
開催地
ジャンル
職種
お問い合わせ先
- 担当者氏名
- 公益財団法人かながわ国際交流財団(大塚・清水)
- 電話番号
- 045-620-5045
- メールアドレス
- mulpa-2025@kifjp.org
- ホームページ
- http://www.kifjp.org/

.png?sv=2024-08-04&se=2026-01-21T22%3A31%3A15Z&sr=b&sp=r&sig=cR1z4QktB6UxVer4GyWWMm%2Bv6tkUNPsAbdBuYQDPM3Y%3D)