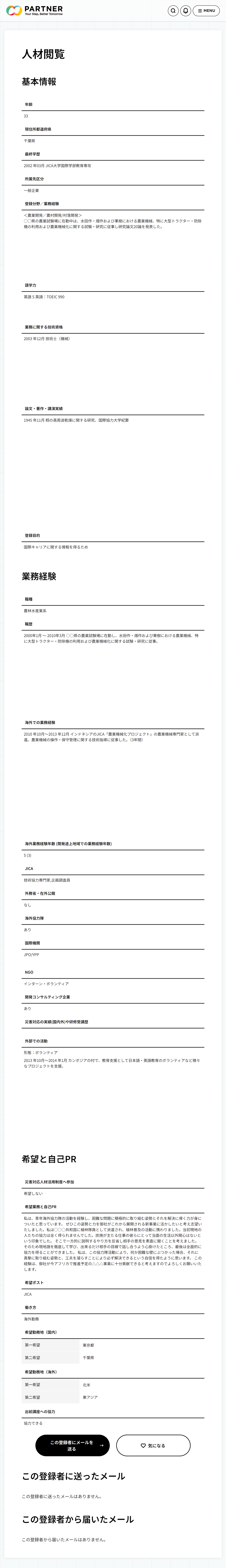コラム 地球規模で生きる人
小畠 瑞代(こばたけ・みずよ)さん(認定NPO法人かものはしプロジェクト ソーシャルコミュニケーション担当ディレクター兼日本事業担当)
「“あなたがあなただから、好きなのよ”―この言葉が、人種や文化を隔てる壁から、私を自由にしてくれた。」
児童買春や人身売買の問題を解決するため、2002年に活動を始めた認定NPO法人「かものはしプロジェクト」。小畠瑞代さんが参画を決めたのは10年前、33歳の時でした。大学卒業後は一般企業に就職しましたが、国際協力への想いを捨てきれず、かものはしプロジェクトへの転職を決意。現在は広報活動や寄付会員とのコミュニケーションを担当しています。学生時代に経験したある出来事をきっかけに、世界の社会問題や国際協力に関心を持つようになったという小畠さん。現在に至るまでの紆余曲折のストーリーを、全3回のシリーズでお届けします。
小畠さんの仕事って、どんなこと?
「子どもが売られない世界」をつくるために活動するNPO法人の一員として、活躍しているよ。
- 認定NPO法人「かものはしプロジェクト」は、どんな活動をしているの?
-
世界では、子どもが物やお金と引き換えに、本人の意思とは関係なく売られてしまうという、児童買春や人身売買の問題が起こっている。
かものはしプロジェクトは、これらの問題を解決するために2002年に立ち上げられた団体なんだ。はじめはカンボジアで、人身売買が起こらない仕組みづくりに注力した。その後カンボジアの経済発展も後押しとなって、児童買春の問題は減少し、2018年にカンボジアでの事業は終了となったの。一方で、南アジアや東南アジアには、まだこの問題が深刻な地域もあって、2012年からはインドで活動を始めたんだ。また、日本での活動も今年からスタートしているよ。詳しくは次回説明するね。
私は今、かものはしプロジェクトの活動を応援してくれる寄付会員とのコミュニケーションの場をつくったり、プロジェクトの活動内容をいろいろな人へ伝える広報活動などを担当しているの。

京都の田舎で、のびのびと育った幼少期。
- 子どもの頃の小畠さんは、どんな生活を送っていたの?
-
私は京都市生まれ。都心からは少し離れた、畑や竹やぶに囲まれているような、ほどよい田舎町で育ったよ。父が高校教師で、帰国子女を積極的に受け入れている学校に勤めていたから、幼い頃から海外が身近だったんだ。自宅でホームステイの受け入れをしたり、私自身も夏休みにニュージーランドにホームステイに行ったりして、とても楽しかったよ。
とはいえ、私はごく普通の子だった。英語と国語は得意だったけど、勉強はそんなに好きじゃなかったし(笑)。そのころは、「将来は海外で働きたい」とか「国際協力の仕事がしたい」なんて、まったく考えてなかったの。楽しいことが大好きで、いつも友達とわいわいしていたタイプだったよ。
留学先で人種差別に遭遇。社会問題について考えるきっかけに。
- 高校は、英語科のある学校に進学したんだね。
-
うん。得意な英語をもっと勉強したくて、英語科を選んだんだ。入学したら1年間、英語圏の国に留学する予定になっていて、「1年間がんばるぞ!」って期待に胸を膨らませていたよ。 ところが…そこで私の人生を決定づけることになる、とてもショックな出来事に遭遇することになったんだ。
- 何があったの?
-
それは、アジア人に対する人種差別だったの。私がただ道を歩いているだけで、差別的な言葉を投げつけられることもあって、辛かった。当時その国は、ちょうど移民が増えていた時期で、アジアから人が大量に流入していた時期だったんだ。そうした変化への拒否反応もあったと思う。でも耐えられなくて、3カ月もたたずに日本に帰ってくることになってしまったの。
それと、日本人としてのアイデンティティをしきりに問われることにも困惑した。過去の戦争やさまざまなニュースについて、「日本人としてどう思うの?」と、意見を求められるけど、そのころの私は、まだ自分が日本人であるという感覚が薄かったから、「そんなこと分からないよ!」って戸惑って…。人種差別やそうした問いかけによって、自分が日本人であることを急激に自覚させられて、コンプレックスを抱えることになって、大好きだった海外も怖くなってしまったんだ。
でも、この留学をきっかけに、「人はなぜ国籍や人種で差別をするのだろう?」と考えるようにもなった。それまでは、恵まれた環境で何も考えずに楽しく生きてきた私だったけど、世界で起きている社会問題にアンテナを張るようになって、時には腹立たしさを感じるようになったんだ。
- 今につながる大事な経験でもあったんだね。高校を卒業してからは、どんな進路に進んだの?
-
高校は楽しく過ごしたけれど、人種差別を受けたときのショックは心にずっと残っていた。日本人であることのコンプレックスも消えなかった。それで、「この気持ちを克服するには、もう向き合うしかない!」と腹をくくることにしたんだ。私は社会学を学ぶことに決めて、大学に進学した。
入学したら、南アフリカに行くつもりだったの。というのも、そのころの南アフリカは、白人と非白人の人種隔離政策「アパルトヘイト」が撤廃されたばかりだった。人種差別の構造を深く知るには、ぴったりの国だと思ったの。でも当時、南アフリカへの渡航は治安上危険だと言われていて、それでも何とか行ける方法はないかと模索していたときに知ったのが「世界青年の船」の存在だった。
「世界青年の船」は、世界各国から18~30歳の青年を集めて、1ヵ月間船上で共同生活をしながら、いろいろな国をまわる内閣府の青年国際交流事業の一つ。募集要項には、南アフリカにも行くと書かれていたから「これだ!」と思ったの。そして、大学2年生のときに応募して、参加が決まったんだ。

恐怖心を取り払ってくれた、バーレーンの友人の言葉。
- 海外が怖くなっていたと話していたけど、船に乗ることに不安はなかった?
-
そのころもまだ人種差別で受けた傷は深く、怖いという気持ちは消えていなかったの。だから、船のメンバーの誰にでも心を開いて仲良くなるってことはできず、壁をつくっていたかな。
でも、そんな状態の私にも、中東のバーレーンから来たNahed(ナヘッド)という友だちができたの。彼女は、さまざまな場面で、私のことを助けてくれたよ。たとえば、私が年上のメンバーに理不尽に怒られて落ち込んでいたときも、「私が意見してくるわ!」って、代わりに言い返しに行ってくれたりね(笑)。とてもありがたかったな。でも、ふと「なんで彼女は、私にこんなに優しいんだろう?」って疑問に思ったの。自分が日本人であることに劣等感もあったからね。だから「Nahed(ナヘッド)は、どうして日本人の私に親切にしてくれるの?」って聞いたんだ。そうしたら彼女は、「ミズヨ。私はあなたがあなただから、好きなのよ。人種も、文化も、性別も、まったく関係ない。愛しているわ」って言ってくれたんだ。それがすごくうれしかったよ。
その瞬間、私が抱えていたコンプレックスも、海外に対する恐怖心も、すっと消えていったの。やっぱり人は、国籍や宗教や性別で差別されるものではない。私は私のままで価値があるんだと、はっきり確信できたんだ。

「世界青年の船」に参加したことで、素敵な出会いに恵まれた小畠さん。コンプレックスや恐怖心を乗り越えたことで、世界の社会問題へ真正面から取り組みたい、という気持ちが生まれてきます。次回は、NGOのインターンに参加したときのエピソードや、一般企業で学んだことなどを紹介するよ!
プロフィール
小畠 瑞代(こばたけ・みずよ)さん(認定NPO法人かものはしプロジェクト ソーシャルコミュニケーション担当ディレクター兼日本事業担当)

NPO法人かものはしプロジェクトの「この問題は必ず解決できる」という信念に共感し、子どもがだまされて売られてしまう問題を世の中に広く理解してもらうため、また自身の経験や知恵をソーシャルグッドに活かしたいという思いから、営利企業での広報、マーケティング、プロモーション職を経験した後、広報・ファンドレイジング(資金調達)担当として2012年7月にNPO法人かものはしプロジェクトに参画。
最近の関心は、イノベーションやフラクタルな世界が生み出されるのは対話の場だと信じて、多様な人が参加できる場作りをすること。システムコーチ。新しくて挑戦できるものが好き。